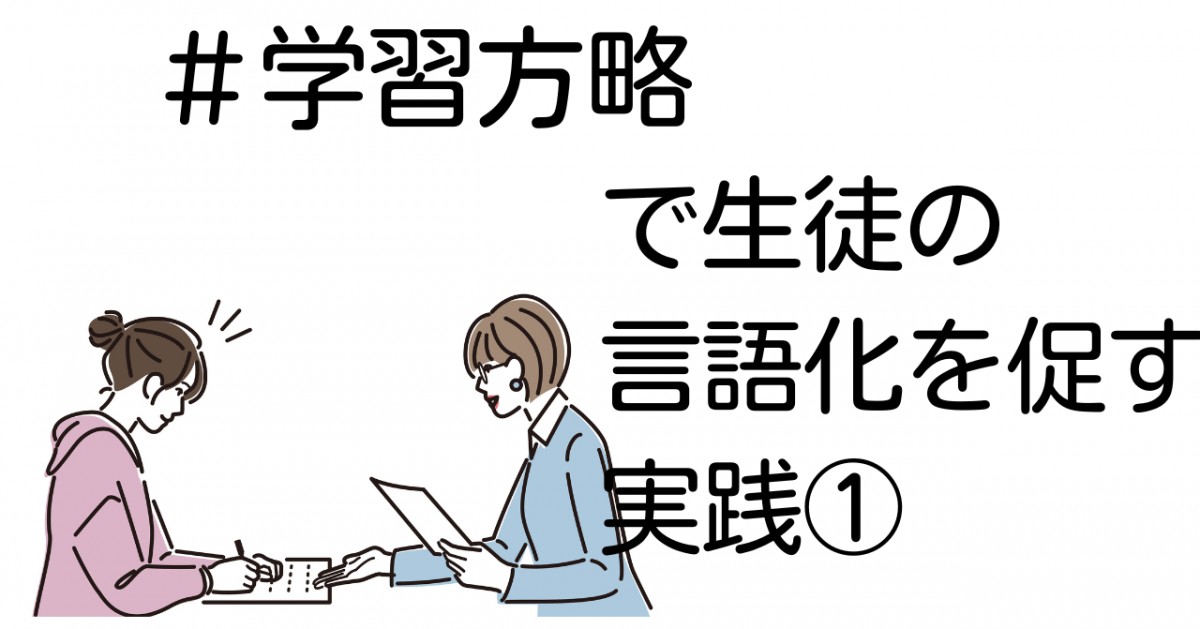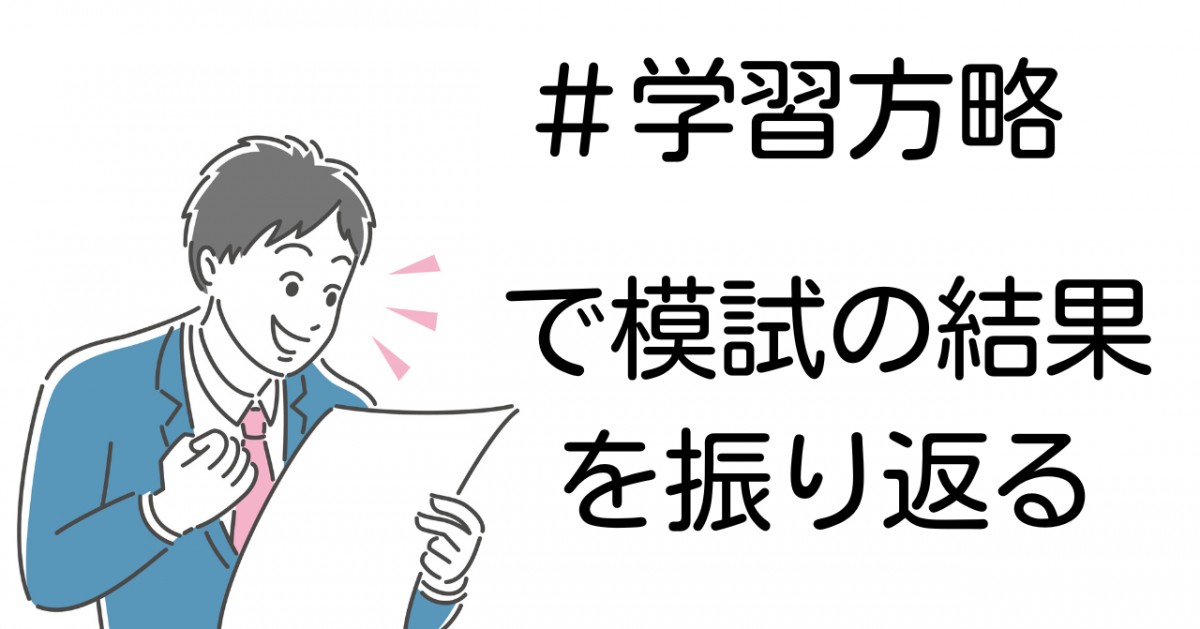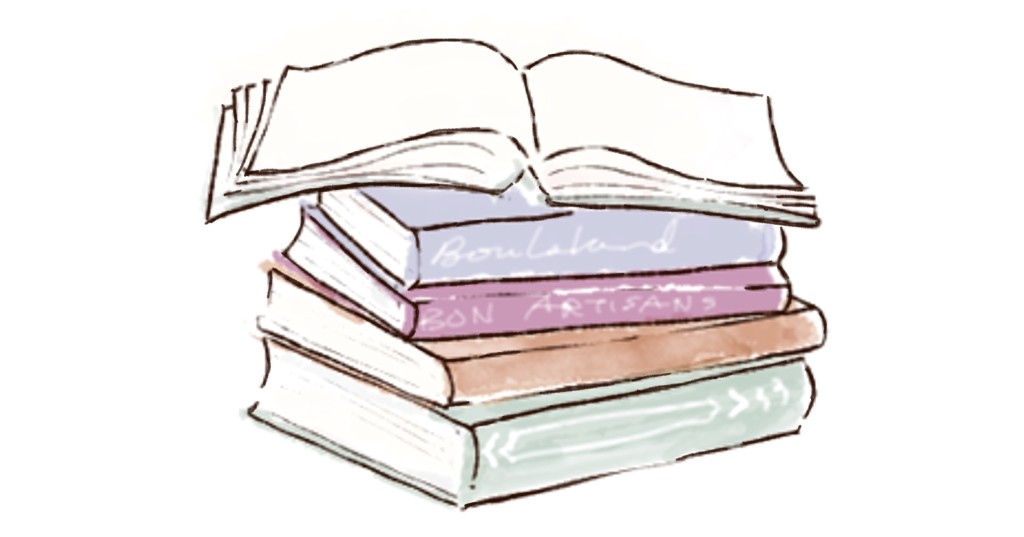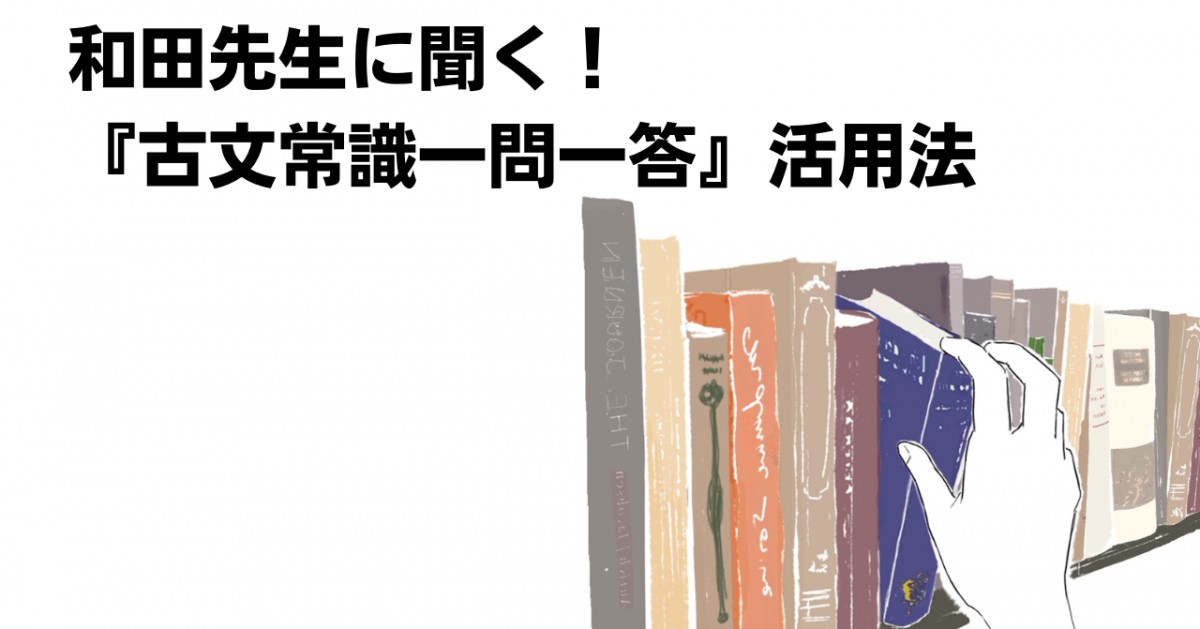国語のケアレスミスをケアする方法
こんばんは、中の人(@mAjorstep_jp)です。クマの被害に関するニュースが後を絶ちませんね。シン中の人と同様に私もキャンプをするので、かなり関心度の高いニュースです。生活圏に出没している地域は気が気でありませんね。昔、林業について授業をしたときに、オオカミが絶滅して増えたシカ被害について取り上げました。シカが下草や木の皮を食べてしまって、森の木々が立ち枯れをしてしまうそうなので、クマの住処や餌にも悪影響がありそうですね。
さて、年末に向けてフル稼働している先生方には、少し気が早いようですが、年始の楽しい学びのイベントについてお知らせがございます!
#小論文添削ライブ202601 開催決定!
昨年度、会員の皆さんの熱いご要望により実現した#添削ライブの開催が決定いたしました!
小論文添削のプロフェッショナル中のプロである根岸先生が、リアルタイムで添削している様子をお届けします。
昨年度は色分けの指導の中でも、珍しい4色使い分けした添削法をみなさんにお届けしました。
今年はどのような内容になるのか、中の人も楽しみです。そして、今回も参考書レビューシリーズで取り上げた参考書をご参加いただいた方に抽選でプレゼントします!
詳しくはまたお知らせいたしますので、続報をお待ちください。では、#小論文添削ライブ202601 の概要をご覧ください。
#小論文添削ライブ202601 概要
日時:2026年1月9日(金) 19時30分 開始予定
場所:Zoomにてオンライン講義
申し込み開始:2025年11月28日(ニュースレターにてお申し込みのご案内を致します)
費用:無料
参加資格:小論文・現代文の指導スキルを学ぶ会ニュースレター会員
ぜひ今のうちにご予定をあけておいてくださいね。(同僚の方にもお声をかけていただけると嬉しいです)
さて、今回の記事は前回の続きです。
前回の記事では次の二つの#学習方略の原則 を取り上げました。
「どうすれば次に同じ間違いをしないか」を考えよ。それを引き出せなければまた同じ間違いをするぞ。1問間違うごとにひとつ教訓を引き出せ。
「勘違いしてました」でごまかすな。「何を」「どのように」勘違いしていたのかを言葉で表せ。わからない? じゃあもう一回問題に戻ってそれをわかるようにせよ。それが「復習」だ。
前回の記事をざっくりとまとめると、振り返りの仕方には段階があり、定期考査や模試でのミスも成功も「なぜ」「どのように」その結果になったのかを自分の言葉で言語化することで、高い効果を得られるというお話でした。
今回は、前回の話をもとに根岸先生に、国語ならではの振り返りの特徴や指導の方法についてお話を伺います。
……本記事のサマリー……
国語という科目において振り返りは他教科と比較すると難易度が高まります。だから「勘違いしてました」「ケアレスミスでした」で終わらせがちです。そこで指導者側が逃げの姿勢を厳しく防ぎ、振り返りの項目をしっかりともち、言語化の習慣づくりをすることで、より効果の高い振り返りをすることができます。
科目による振り返りの難しさ──国語はなぜ複雑か
中の人:根岸先生、前回は振り返りの言語化が大変重要である、というお話をありがとうございました。振り返りを数学や英語で行うのであれば、ミスした部分を言葉にするのはとても簡単な印象を受けました。一方で国語の振り返りってとても難しい気がします。
根岸先生:非常に核心をついていると思います。数学の場合、失敗の原因が比較的明確なんです。計算ミスなのか、定義の誤用なのか、手順の抜けなのか。つまり、誤りを構造的に整理しやすい。
ところが国語は複合的です。設問文の読み違え、文脈の把握ミス、語彙理解の不足、選択肢の比較が甘い、というようにいくつもの要因が絡み合います。
だから「一回教訓を引き出したからといって、同じタイプの問題で必ず解けるようになる」とは限りません。
それでも、「どんな失敗をしたのか」を意識的に記録していくうちに、傾向が見えてくるんですね。たとえば、「私は選択肢を根拠と照合せずに直感で選んでしまう」とか、「筆者の意見と自分の意見を混同しやすい」とか。これがわかれば、次のステップに向けた自己修正が可能になります。
(中):自分の傾向と対策、になるんですね。国語で発生したミスについて言語化することはイメージができたのですが、一番メタ化ができている優秀な生徒の「成功についての言語化」はどのようにしたらよいですか。
(ね):できる子の振り返りは難しいですよね。