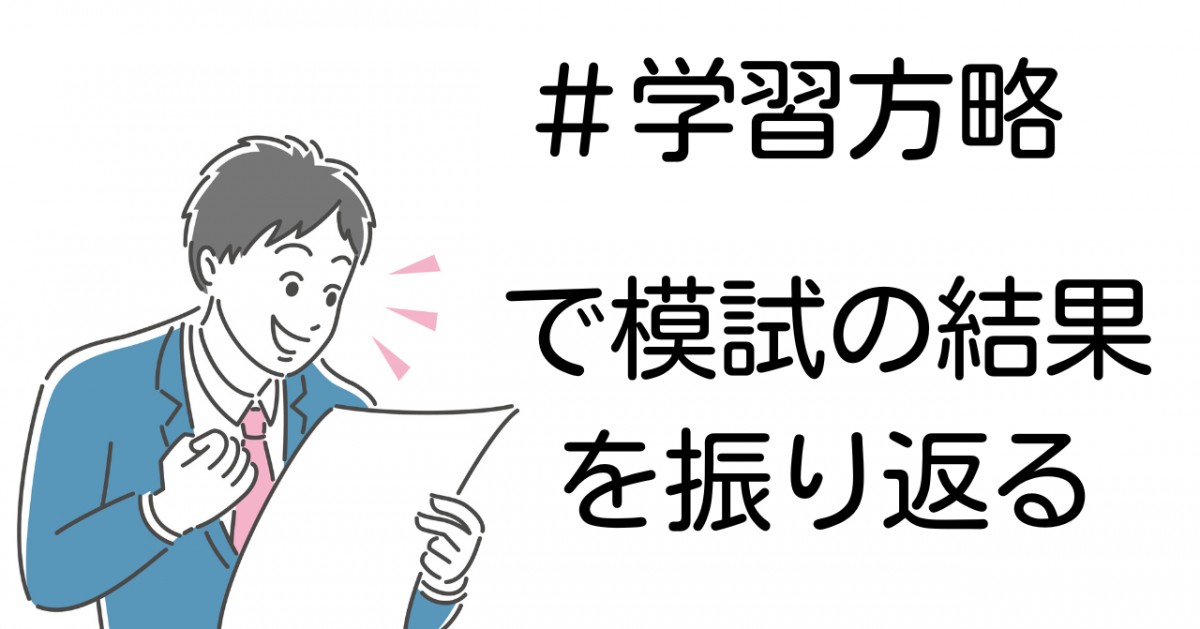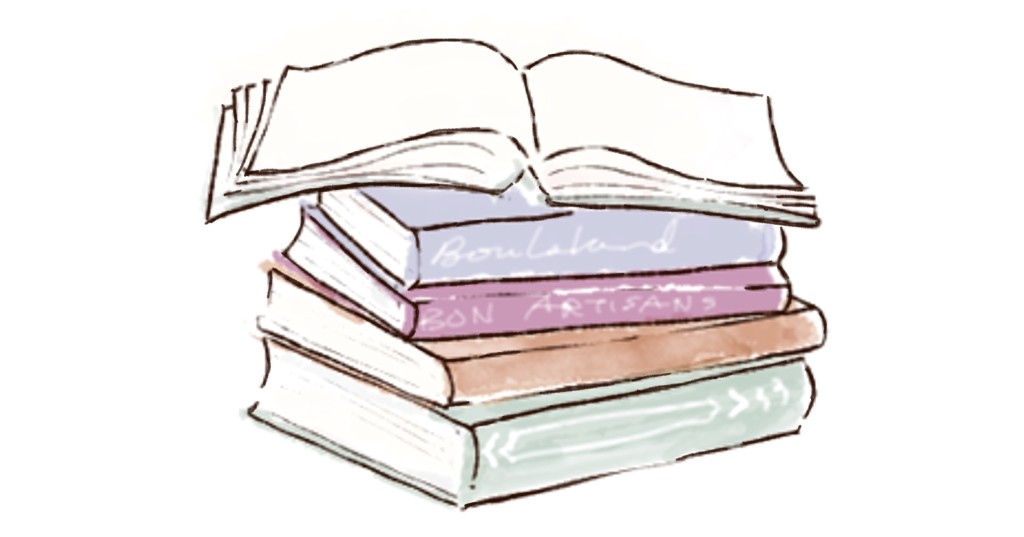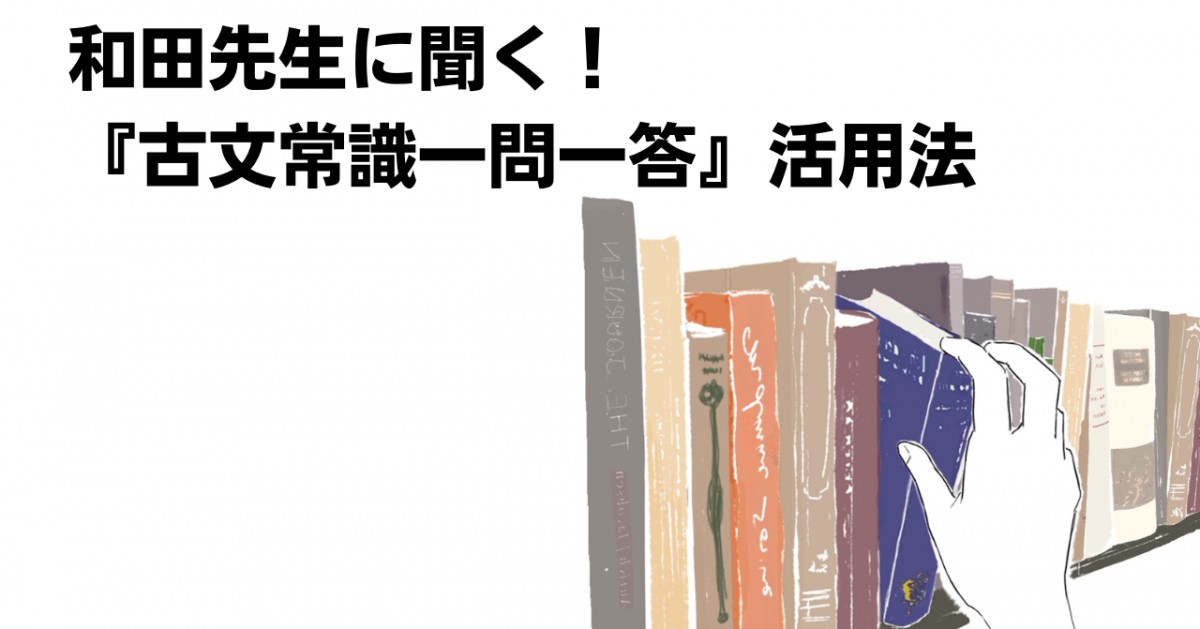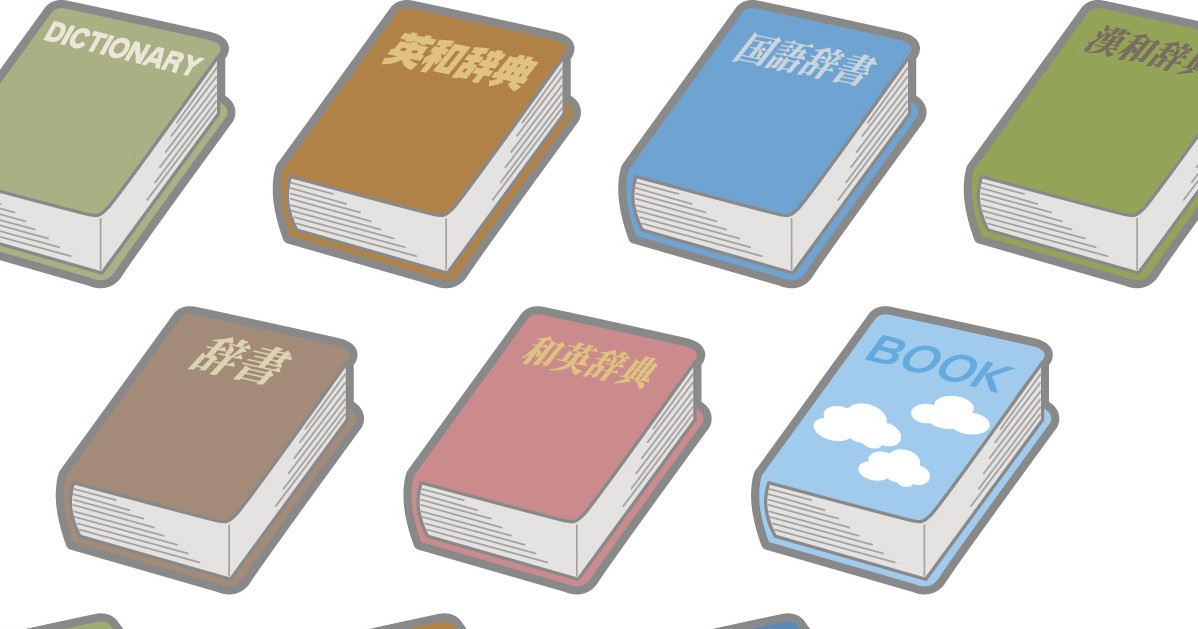間違いを“教訓化”せよ──根岸先生に聞く、学習方略の核心
こんばんは、中の人(@mAjorstep_jp)です。
ぐっと冷え込んできましたね。コンビニにおでんの機械がセットされていました。昔からおでんはお米が進まないという理由で好きではなかったのですが、娘にせがまれておでんを用意したらとても美味しかったです。いい記憶に上書きできてよかったと感じました。娘に今度はおでんを串に刺してくれとオーダーが入りました。(調べたら、△はこんにゃくで定番ですが、◯は卵か大根、□ははんぺんやちくわなどの練り物など諸説ありますね。)
さて、今回は#学習方略の原則 のなかから、明日にでも生徒に伝えたくなる理想的な復習のあり方について詳しく根岸先生にお伺いし、ポイントを絞ってお伝えします。
……本記事のサマリー……
本記事では、根岸先生が語る間違いの扱い方が学びの質を左右するという学習方略を紹介しています。単に「間違えた」「勘違いしていた」で終わらせず、「なぜ」「どのように」間違えたのかを自分の言葉で言語化することが、真の学びに不可欠だと説きます。間違いを分析せずに次へ進むと、同じ誤りを繰り返してしまいますが、言語化を通じて自分の思考の構造を捉え直すことで、学習は経験へと変わります。また、復習における生徒の学びの段階を解説。言語化は理解の曖昧さを可視化し、学びの「解像度」を高める鍵となります。
「間違い」をどう扱うかが、学びの質を決める
中の人:今回はこちらの学習方略について根岸先生にお話をうかがいます。
「どうすれば次に同じ間違いをしないか」を考えよ。それを引き出せなければまた同じ間違いをするぞ。1問間違うごとにひとつ教訓を引き出せ。
先生の「一問間違えるごとに一つ教訓を引き出せ」という言葉、これがすごく印象的だと感じました。生徒に指導するうえでも、評価やフィードバックの根幹に関わる考え方だと感じています。まずこの言葉に込めた意味から教えてください。
根岸先生:簡単に言えば、「どうすれば次に同じ間違いをしないか」を考えることが、学習の本質だということです。多くの生徒は「間違った」「わからなかった」で終わってしまう。そこをもう一歩踏み込んで、「なぜ間違ったのか」「どのようなミスが発生したのか」を自分の言葉で表現することが大事なんです。
もしそれをしないまま次の問題に進んだら、同じタイプの誤りを繰り返すことになります。だからこそ、私はいつも「一問間違うごとに一つ教訓を引き出せ」と言っています。
これは単なる精神論ではなく、学習方略の原則です。間違いという出来事を「経験」に変えるには、反省ではなく言語化が必要なんですよ。
「勘違いしてました」で終わらせない
(中):生徒の振り返りを見ていると、「あ、勘違いしてました」で終わってしまうケース、よくありますね。
(ね):そうなんです。こちらの学習方略ともつながる部分がありますね。
「勘違いしてました」でごまかすな。「何を」「どのように」勘違いしていたのかを言葉で表せ。わからない? じゃあもう一回問題に戻ってそれをわかるようにせよ。それが「復習」だ。
この「勘違いしてました」という言葉ほど危険な言葉はありません。「勘違いしていました」で終わると、学びのプロセスが断ち切られてしまいます。
私は授業でも個別指導でも、「その“勘違い”って何?」「どこで?」「どういうふうに?」と必ず問い返します。
生徒が「わかりません」と答えたら、「じゃあもう一度文章/問題に戻ろう」と促す。それが本来の「復習」です。復習とはもう一度問題に取り組むことだけではなく、もう一度間違いを振り返り、理解し直すことです。この視点を持つだけで、学びの密度はまるで変わります。
学びの段階──「見るだけ」から「言語化」へ
(中):なるほど。生徒に復習の指導をするときに、ポイントとなる考え方はありますか。
(ね):はい、私は学習者を段階的に分けて考え、生徒の学び方をいくつかの段階に分けて考えます。
まず最初の段階にいる生徒は、「答えだけを見て終わる」タイプです。成績が伸び悩む子はほとんどここにいます。過程を振り返らないから、何をどう考えたかが本人にも見えません。
答えのページを開いて正答を確認しただけでは、頭をほとんど使っていない状態ですから、記憶に残りづらいでしょう。
次の段階に上がると、解説を見るようになります。これは大きな前進ですが、まだ受け身の状態です。解説を読んだだけで理解した気になって満足してしまうからです。
(中):多くの生徒さんはこの段階だと思います。次の段階があるのでしょうか。