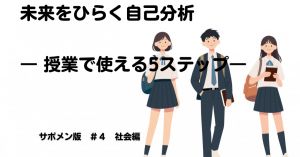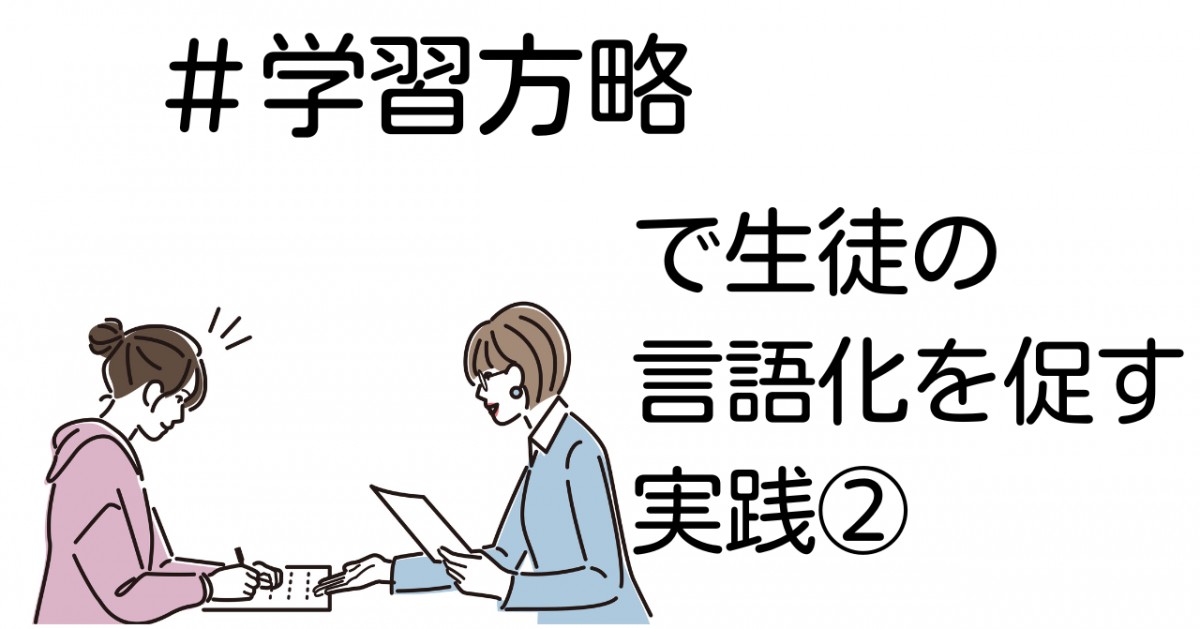未来を描かせる!学びと行動の“設計図”を一緒に作る
こんばんは、シン・中の人、一ノ瀬(@mAjorstep_jp)です。
先日、約3か月間ずっと言いたくて言いたくて震えていた二文字を口にすることができました。やっと言えるのか、やっとこの時が来たのかと、涙を堪えながら言いました。「寒い」!!!!!!!!暑さに耐えることから解放されることが、ここまで素晴らしいこととは思いませんでした。ありがとう夏。もう当分会いたくないです。
さて、新シリーズ「未来をひらく自己分析 ― 授業で使える5ステップ」と題し、現高1・2年生向けの自己分析の具体的な方法をお届けしております。第一回は生徒に”自己分析”の意味を伝える大切さ、第二回は過去、第三回は現在、第四回は社会に着目した自己分析の方法をお送りしてきました。
まだの方はぜひこちらから!
最終回は、 時系列に沿った自己分析のうち「未来」を考える方法についてです。ここでも自分と社会のつながりを考えることが大切です。また、望む未来を実現するためのマインドや、道筋の発見の方法も学びます。
メイジャーステップの根岸です。X:@DiceK_Negishi
本シリーズもいよいよ最後となりました。過去・現在・未来のうち、最後は未来です。
未来を語れというと夢のようなことばかり書く生徒も少なくありません。あるいはきれいごとを並べるだけとか。指導者としてはなかなか頭の痛いところです。
では、どうすれば現実的に、かつポジティブに未来を想像することができるでしょうか。いくつかノウハウがあるのですが、今回はその一部を紹介します。
ちょっとしたマインドセットや言葉の使い方で、生徒の思考が、想像力が動き出します。教室の生徒さんの未来予想図にちょっとしたお手伝いができるのではないかと思っています。ご期待ください。
授業のねらい
最終講のねらいは以下の2点です。
・世界の未来像と自分の未来像をつなげる
・未来を実現させるためのマインドを身につける
「私は将来こうなりたいです」と語れる生徒は多いです。しかし、そこには「社会」の視点が抜けて落ちています。このシリーズを通して一貫して伝えていることは、自分と社会はセットで考えるということです。あなたが理想とするのはどのような世界か?まずはこの想いを先行させることが重要です。生徒一人一人が理想とする未来像をポジティブに描かせること。そこに自分はどう関わるのかを想像させること。これからの未来社会をつくるのは目の前の子どもたちです。未来を担う子どもたちの背中を、力強く押して参りましょう。
未来の世界に、私の線を引く
世界の未来像と自分の未来像をつなげることから始めます。
まず、数十年後に「世界が」「社会が」どうあるべきか。そのために自分が「どうありたいか」「何をしたいか」を考えます。
ここで大切なことは「なりたい」ではなく「ありたい」ということです。
「なる」は、これからだんだんそうなっていくというイメージです。一方「ある」は明確にそこに存在しているということです。「未来に私はこういう存在であることが確定している」という強い意志を含ませます。
未来が先に決まっていて、そこに向けて自分はどうするか。あるいは、そこから逆算してこれからどういう人間として成長していくべきかということを考えることが大切です。つまり、未来の自分はすでにどうあるべきか。ということです。ここからおのずと自分が今やるべきことも見えてくるはずです。
繰り返しになりますが大切なことは、世界・社会の未来像と自分の未来像をイメージし、両者をつなぎ合わせることなのです。
未来を描き、そこに立つ自分を考える
未来像と自分の未来像をつなげるための具体例を紹介します。