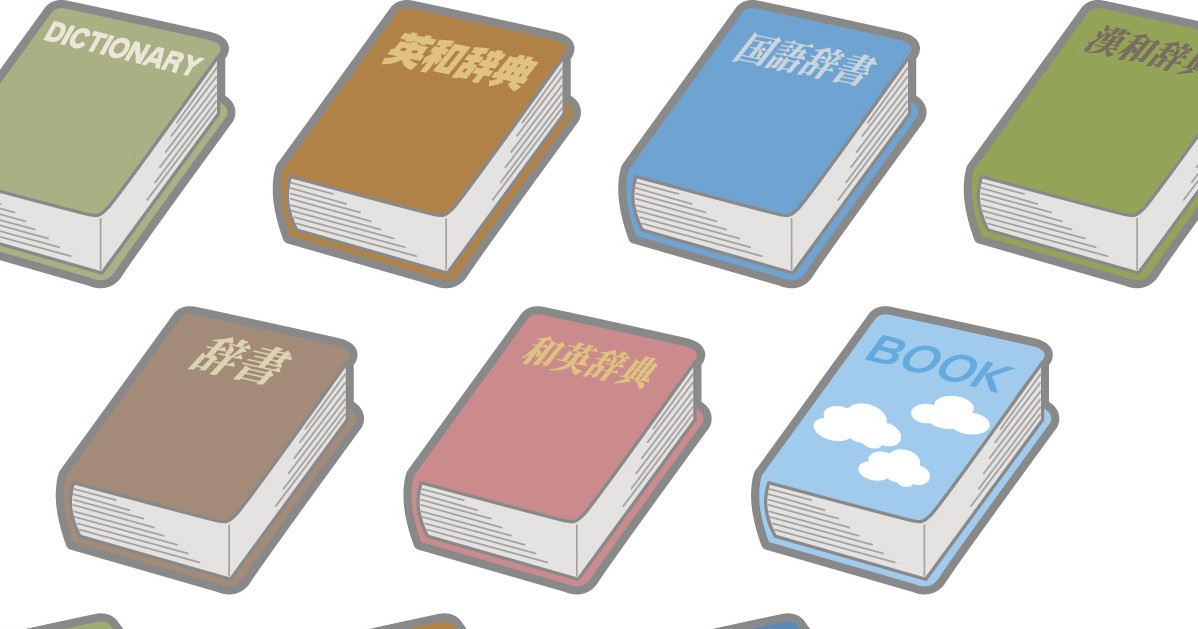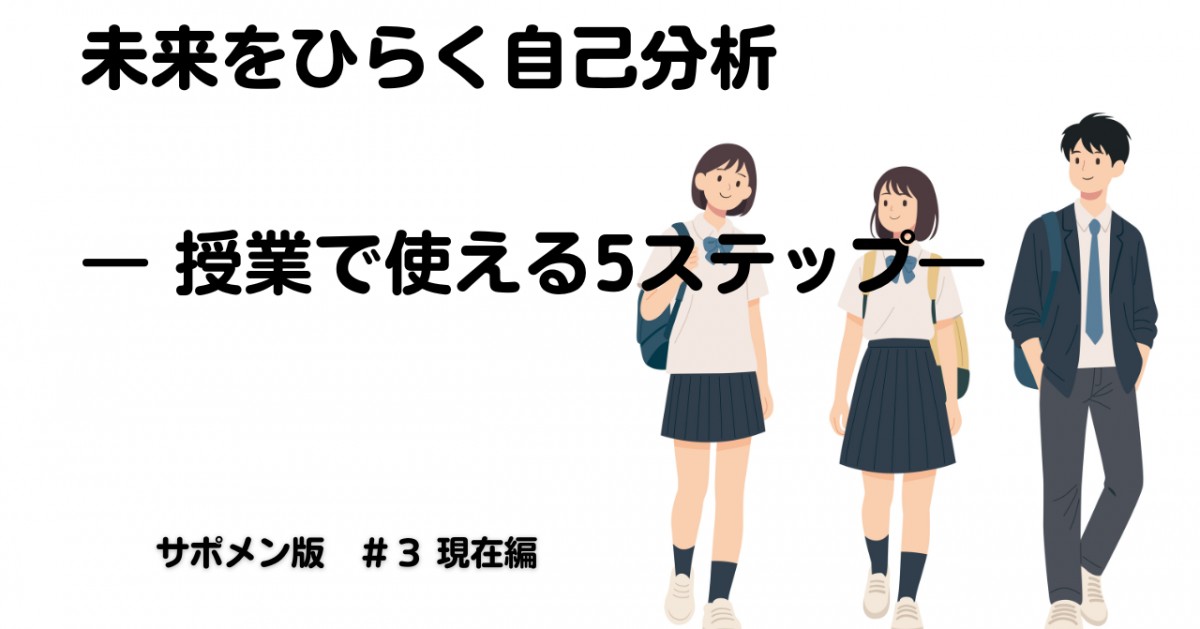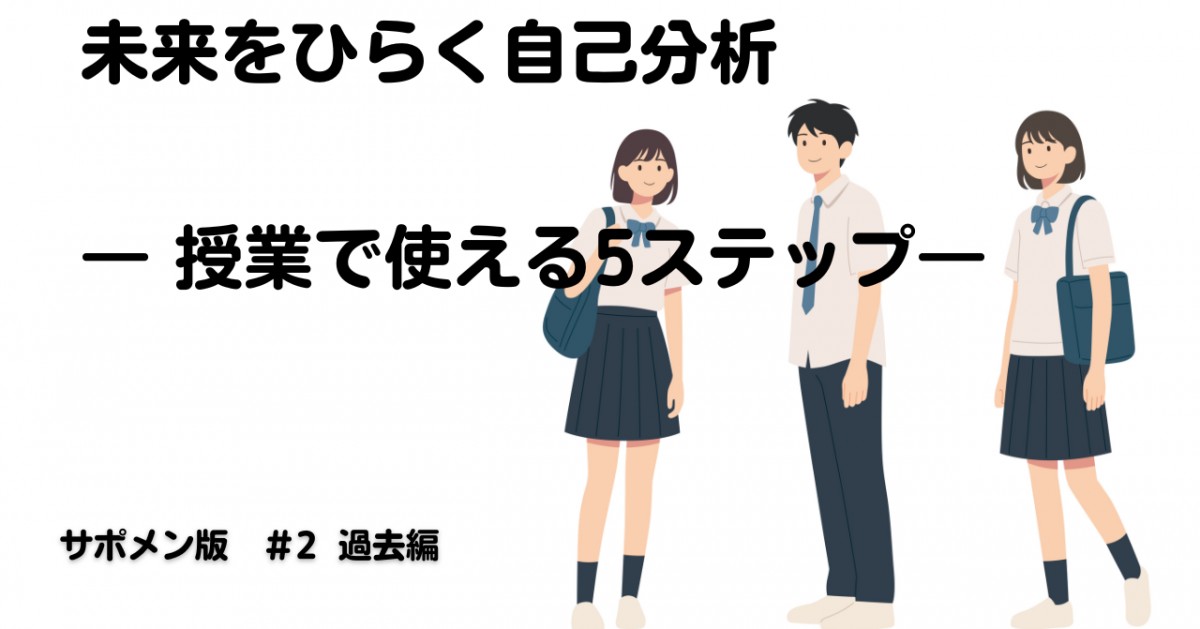記述・抜き出し・選択肢、どうやって決める?
こんばんは、中の人(@mAjorstep_jp)です。娘も大きくなり、だいぶ余裕ができたので今まで手つかずだったゾーンを片付け始めました。「こんなの買ってたっけ」がたくさんありまして、もっと吟味して買うべきだった、買ったなら有効活用しないともったいないと反省続きです。冬になりもっと寒くなればきっと縮こまって、何をするにも億劫になってしまうのでこれを機に家をスッキリさせたいです。
さて、今回は会員様からのご質問にお答えするコーナーです。早速根岸先生にお答えいただきましょう。
……本記事のサマリー……
作問において、設問形式の選択基準とは何か? 読解問題を作るうえで記述・選択・抜き出しそれぞれに向き不向きがあります。ですが、まずは記述式で答えを作るのが原則。その後、それぞれの特徴を理解し、柔軟に形式を選びます。この記事ではその方法について解説します。
メイジャーステップの根岸です。X(Twitter):@DiceK_Negishi
ニュースレター「小論文・現代文の指導スキルを学ぶ会(β版)」今号はいただいたこちらのご質問にお答えします。
記述、選択肢、空所補充と様々な形式の設問がありますが、根岸先生はどのように使い分けていますか?何か基準があれば教えてください。
今回は設問形式の選択についてのご質問です。マークシート方式なら選択式問題しか出題できません。すべて記述式問題にしたいところですが、時間的制約からなかなか難しい。
抜き出し問題ばかりにすれば、読解というより「目の検査」になってしまいます。しかし、どの形式を選択するかはけっこう難しいものです。
そこで、今回は根岸がどのように設問形式を使い分けているかについて書きたいと思います。
選択肢、抜き出し、記述のをどう決める?
結論から申しますと、根岸はこうやって設問形式を選択しています。
-
まずは記述式で答えを作る
-
生徒が書けそうな答えになったら記述
-
難しそうなら選択肢
-
特定の条件下にあれば抜き出し
-
時間と形式の縛りの中で可能な範囲で記述に戻す
1. まずは記述式で答えを作る
いろいろな機会でお話ししていますが、読解問題の作問は「答えが先、問いが後」が原則です。
より正確に言えば、「答えと問いが同時に思い浮かぶ」もしくは、「この部分、この段落、この範囲のxxという内容を読み取ってほしいという思いが先」です。
先に線を引いて「さて、答えをどうしようかな」などとやっているから、いつまでたっても作れたり作れなかったりするんです。
答えさせたい内容が見つかったら、記述で答えを作ります。字数とか、本文中の言葉を使うか否かは気にせず、答えさせたい内容を書きます。字数も本文中の言葉の採否も設問を作る段階で決めることです。
答えに違和感がなければ次へ進みます。
2. 生徒が書けそうな答えになったら記述
テストの対象生徒が1. の答えを書けそうなら、記述式問題にします。問いと条件を決めていったん完成です。あとで変わる可能性もあるので、あくまでいったんです。
3. 難しそうなら選択肢
生徒が記述で書くのが難しそうなら、自分が書いた解答を正解とする選択式問題にします。この時点で選択肢の長さは考えません。後で変わる可能性もあるので、あくまでとりあえず、です。
4. 特定の条件下にあれば抜き出し
抜き出し式問題にするのは、自分で書いた答えが特定の条件下にある場合です。
その条件とは……