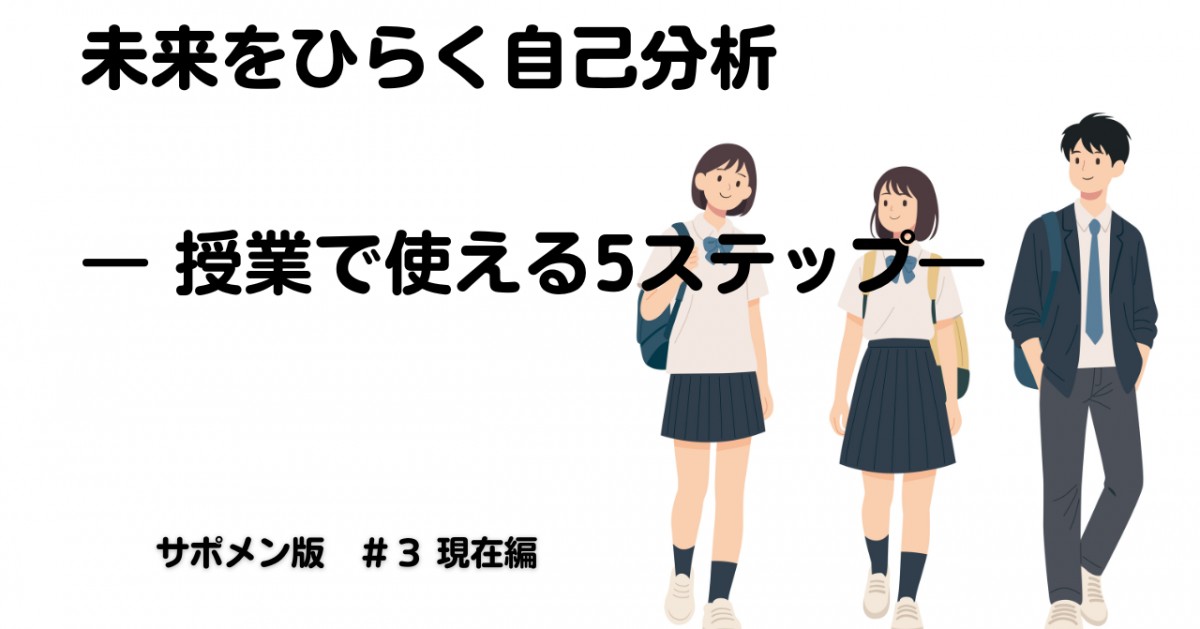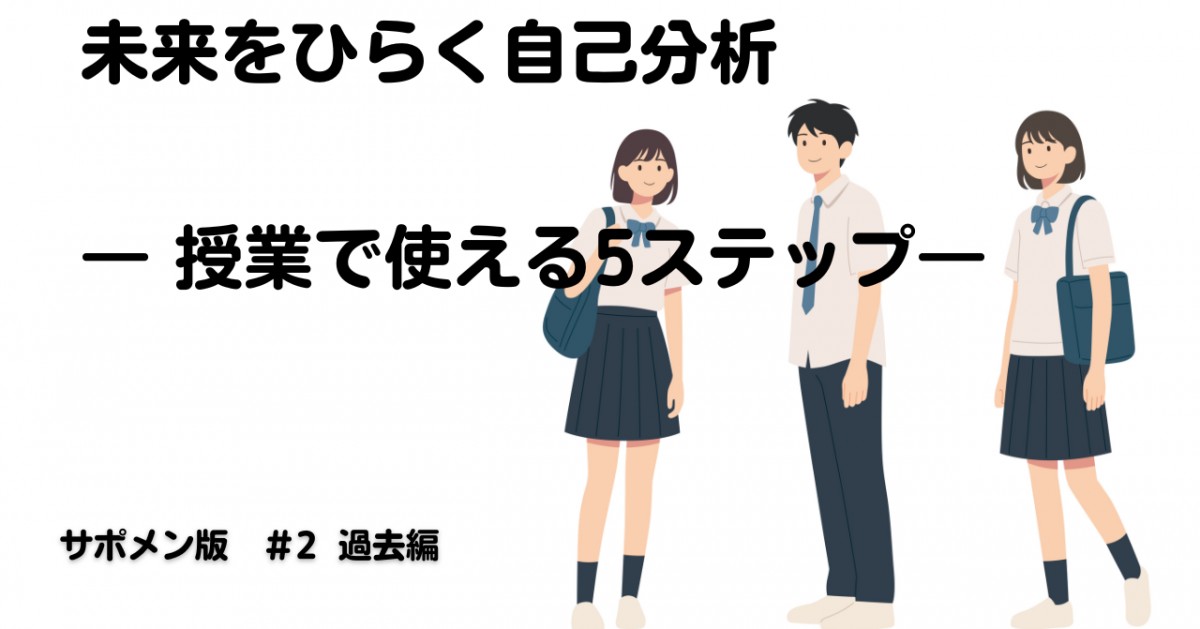スマホに頼らず、語彙指導。
こんばんは、中の人(@mAjorstep_jp)です。玄関の外に黒いヤツがいたので、「侵入許すまじ」と、逃げ場になりそうな傘をどかして退治をしました。その傘がドアに挟まっていることに気が付かず隙間から飼い猫が脱走してしまうという失態を犯しました。
3時間にわたり何度も発見するものの、元野良猫のため久しぶりのお外を大満喫している猫様にフル無視を重ねられました。どうにか道路のほうにでないように近所をウロウロし、声をかけました。お腹が空いたころ自力で家に戻ったので事なきを得ました。本当に血の気が失せました。
今彼女は虫かごに入ったカナヘビをご満悦で眺めています。
さて、今回は、質問をいただきましたので早速根岸先生に解答をいただきたいと思います!
……本記事のサマリー……
スマホやタブレットを使うことで、辞書の使用に距離ができてしまっている昨今の生徒に対して効果的な語彙指導は何か。それは、グループ活動での語彙学習と学習学校図書館との連携が考えられる。辞書の引き比べをはじめとした言語活動や司書と綿密な打ち合わせをした図書館での学習活動、そして辞書そのものに興味をもつためのおすすめの本も併せて知ることができる。
いつも勉強させていただきありがとうございます! 授業中の語彙指導についてお聞きしたいです
偏差値62くらいの単位制の高校に勤めています タブレットは配布されていないので、紙・電子問わず辞書を持っている生徒は持ってくるように伝えているのですが、持っていない生徒に対しては購入を強く勧める事が難しいため、どうすればよいか模索中です。
生徒所有スマホの検索機能も手段の一つかと思うのですが、ロック画面を開いた瞬間生徒の頭が授業からプライベートモードに移ってしまう感じがしてなかなか積極的にスマホを使おうという気持ちになれません。 語彙指導について何かアイデアがありましたら教えていただきたいです。
こちらの質問に回答します。
メイジャーステップ根岸です。Twitter:@DiceK_Negishi
語彙の指導についてご質問ありがとうございます。語彙指導では徹底的に辞書を引け、と言っている根岸ですが、キーワード集も適宜取り入れています。辞書の引き方もいつか記事にしたいですね。また別の機会に。
ご質問者様の気にしているところって、この点だと思うんですがいかがでしょうか。
タブレットは配布されていないので、紙・電子問わず辞書を持っている生徒は持ってくるように伝えているのですが、持っていない生徒に対しては購入を強く勧める事が難しい
タブレット、持たせたいですよね。予備校の授業ではなかなか難しいのですが、学内予備校で出講している学校でiPadやchromebookが配布されており、ときどき使わせています。いろいろな学校に行って様子を観察していると、ICT活用は中学高校より小学校の方が進んでいる印象です。校種を超えたICT活用の勉強会なんかも企画したらおもしろいのかもしれません。
個人での購入を強く勧められないのであれば、他の手段を考えるしかない、だけどどうしたらいいかわからない……というのがご質問者の先生の悩みですよね。
さて、質問へのお答えですが、二つアイデアがあります。
-
グループ活動での語彙学習
-
学校図書館との連携
順番にお話しします。
1. グループ活動での語彙学習
辞書を持っている生徒と持っていない生徒をグループにして学習活動を行う、というのが最もシンプルなやり方になるかと思います。
グループで語彙のマインドマップを作成する活動を小学生指導でやったことがあります。真ん中に難しめ、語義多めの語を置き、辞書で意味を引きながらマインドマップ(連想ゲーム?)を作成します。
知らない言葉を辞書で引いても語釈の言葉がわからない……という経験を小学生はたくさんしているんですよ。それなら語釈中のわからない言葉を調べればいいかというと、それもわからなかったり、循環したりして、どうにもならないことも。
それなら、異なる辞書を持っている子たちをグループにし、辞書の引き比べをしてわかりやすい語釈を手に入れたり、その語釈をもとに次の言葉を調べたりして、言葉のネットワークを広げていけるんじゃないかと思うんですよね。
これ、異なる辞書っていうのがポイントになるの、わかっていただけますよね。語釈の違いに触れる機会ってあまりありませんからね。
実際やってみると結構大変なんですが、辞書への親しみであったり言葉への関心の喚起であったり、意味があったのかなとは思っています。
ちなみに、辞書の活用では中部大学の深谷圭助先生の「辞書引き学習」が有名ですね。
深谷先生が監修された『大人の国語やりなおしドリル』(笠倉出版社)がなかなかいい本なのでおすすめします。
表紙には出てないのですが、中扉に問題作成協力の先生の名前が載っています。根岸大輔先生っていう方なんですけどね。収録されている問題はすべて根岸先生が作ったんだそうですよ。さすがですね、いい問題がズラリと並んでいます。Kindleアンリミテッドで読めるそうですのでぜひ。
……以上宣伝でした。
2. 学校図書館との連携
本件、図書室での学習活動を考えるのがよいと思うのですが、いかがでしょうか。書架に国語辞典を置いているでしょうし、国語辞典以外の辞書に触れたり、辞書の使い方、調べ物のしかたを学んだりできるのではないかと思います。司書教諭、図書館主任の先生と連携する(ご質問者様がそうかもしれませんが)ことで、指導のアイデアがたくさん出てきそうです。