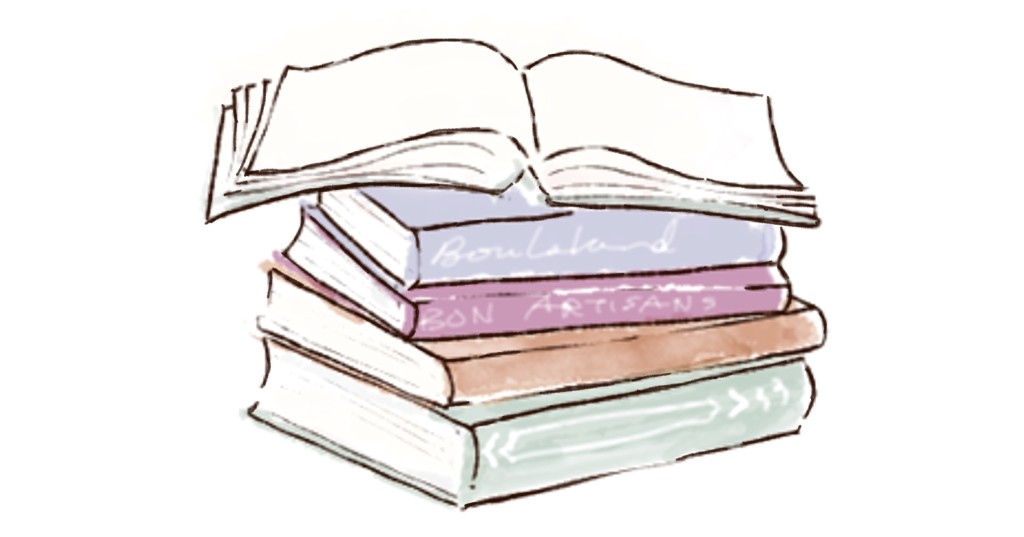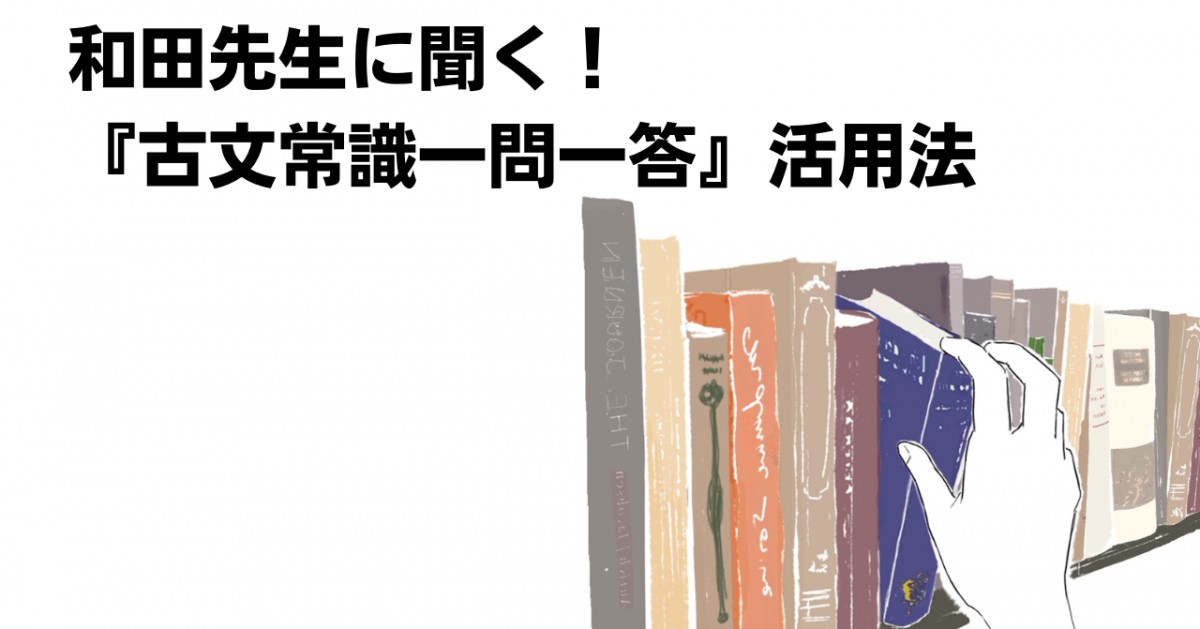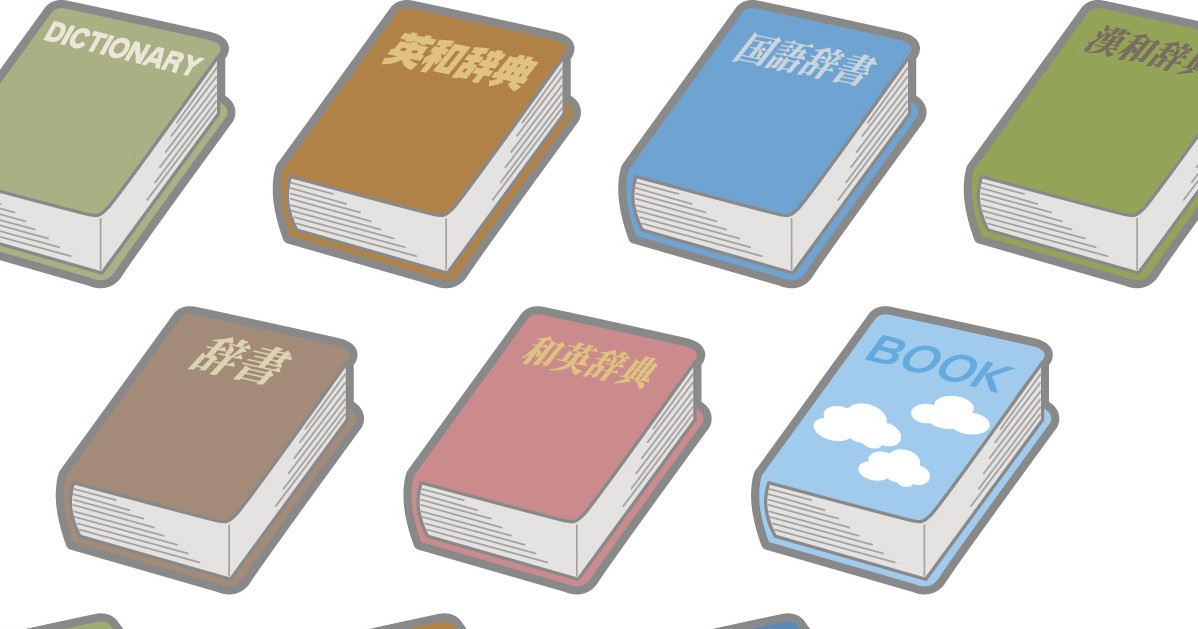小論文の文体を即ブラッシュアップする方法 6選
こんばんは、中の人(@mAjorstep_jp)です。娘のバレエの先生のご家族や、夫の職場もインフルエンザの波が迫っています。娘も風邪を引いて微熱を出しました。今からでも遅くはありませんのでインフルエンザのワクチンを打って、年内の残り二ヶ月を乗り切りたいものです。
前回の記事では小論文の過去問指導において、解答用紙の形式と時間についてのお話をしました。
今回は、経験の少ない生徒たちの文章がすぐに小論文「らしさ」を帯びるようになる書き方を6つ選んでお伝えします。
-
訓読みを書きたくなったら……
-
読点の打ち方の簡便な基準
-
できれば避けたい接続語
-
文の書き出しのテクニック
-
人称代名詞のテクニック
-
受け身の文のテクニック
……本記事のサマリー……
前回の記事で扱った「解答用紙の形式と時間配分」に続き、今回は小論文の文章を一気に“それらしく”見せるための6つのテクニックを紹介します。たとえば、「~を行う」を「推進する」に変えるだけで文がぐっと引き締まる――そんな言葉選びの工夫から、「なぜなら」「たとえば」をあえて使わないことで論理を明確にするコツ、さらに「人の気配を消す」文章術まで。どれも、経験の浅い生徒の文章が短期間で変わる具体的な指導ポイントです。文体の印象を整えることは、内容をより的確に伝える第一歩となります。読後、すぐに実践したくなる“文章の磨き方”を、根岸先生が徹底解説します。
① 訓読みを書きたくなったら同じ意味の二字熟語に変換する
いわゆるサ変動詞が上手に使えるようになると、堅い上手な文章にできるんです。実際に例を見てみましょう。
-
~について考えるべきである⇒検討すべきである
-
~を広めなければならない⇒展開する必要がある/普及させることが第一選択肢となる
-
~を行う⇒推進する
-
~という時代が来る⇒到来する
「熟語+するの形で表せないか?」と考えるよう指導すると生徒もわかりやすいのではないでしょうか。
② 点の打ち方
「述部が出てきたら打つ」と指導します。大抵の生徒は、章を読んだり書いたりするときに文節や品詞を意識していません。私たちは思いますよね。古文では自立語付属語、品詞を意識するのに、現代文では意識しないよな……って。読点の打ち方はまさにそれです。
③ 接続語の使い方
メイジャーステップでは、接続語を「使い過ぎない」「真に必要なものだけ用いるように」と指導しています。
「真に必要でない接続語」の典型は「なぜなら」です。小学生の低学年ではこれでもかと教え込まれている形ですね。もちろん重要な表現ではあるのですが、上手に使わないと小学生レベルの文章になってしまう。幼稚な印象を与えてしまいかねません。もう一つやっかいなのが「たとえば」です。自分の意見の裏付けや根拠を提示したいときに、生徒はつい使いたくなってしまいます。例はあくまで例でしかないのに、主張の根拠にしたくなってしまうのです。
「なぜなら」と「たとえば」の大きな弊害がもう一つ。そのあとに続く文章の筋道が通っていないことを見失わせてしまうのです。「なぜなら」と書いた瞬間に理由を述べた気になる、「たとえば」と書いた瞬間適切な例を挙げた気になってしまう。こんな失敗を誘因するものはなるべく「使わない」と決めてしまった方が安全です。実際、「なぜなら」「たとえば」は使わなくても意味が通じます。「なぜなら」と書かなくても文末は「……からである」になるし、「たとえば」を使わなくても個別の事例は述べられる。自分を混乱させる言葉は使用を避けた方がよいでしょう。
④ 文の書き出しを 「~は」にしない
「〜は〜である。」という形を連発すると幼稚な印象を受ける文章になってしまいます。たとえば歌舞伎について論じる小論文の書き出し。
-
歌舞伎は伝統文化のひとつである。
-
日本の伝統文化のひとつが歌舞伎である。
あるいは、ケアの倫理について論じる小論文。
-
現代社会の変化の中でケアの倫理に光を当てられた。
-
現代社会の変化の中で光を当てられたのがケアの倫理である
スポットを当てたい言葉は主部に置きたくなります。しかしそれを述部に置くことで目立つようになりますね。特に一文節で表現できる言葉を主語にするのは極力避けます。
⑤ 人の気配を消す