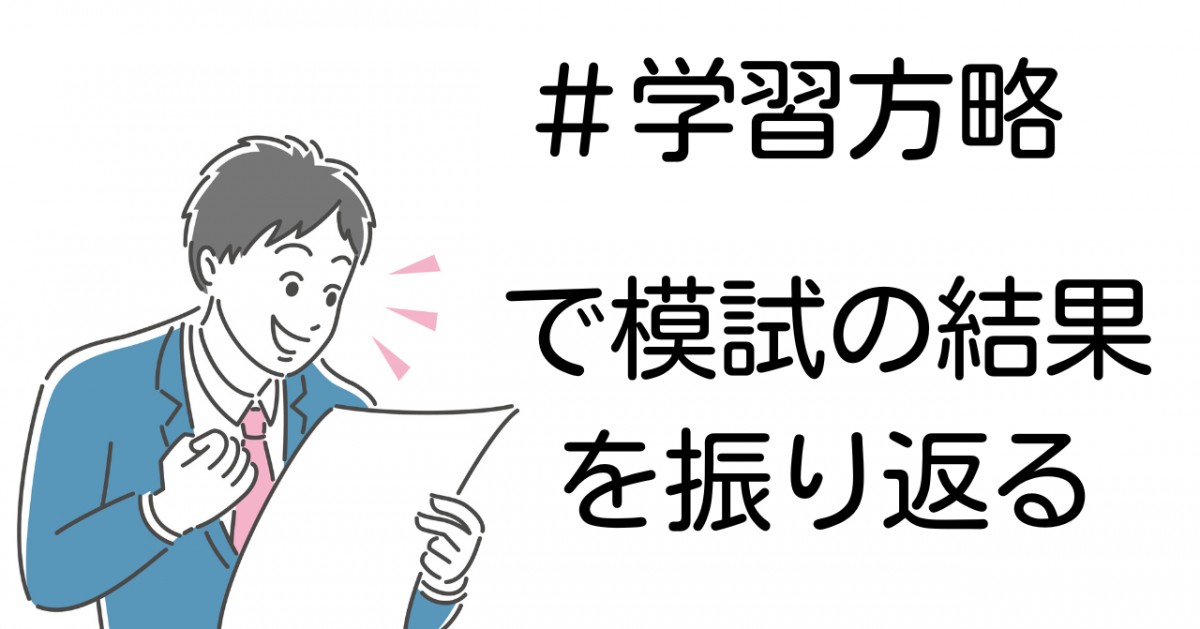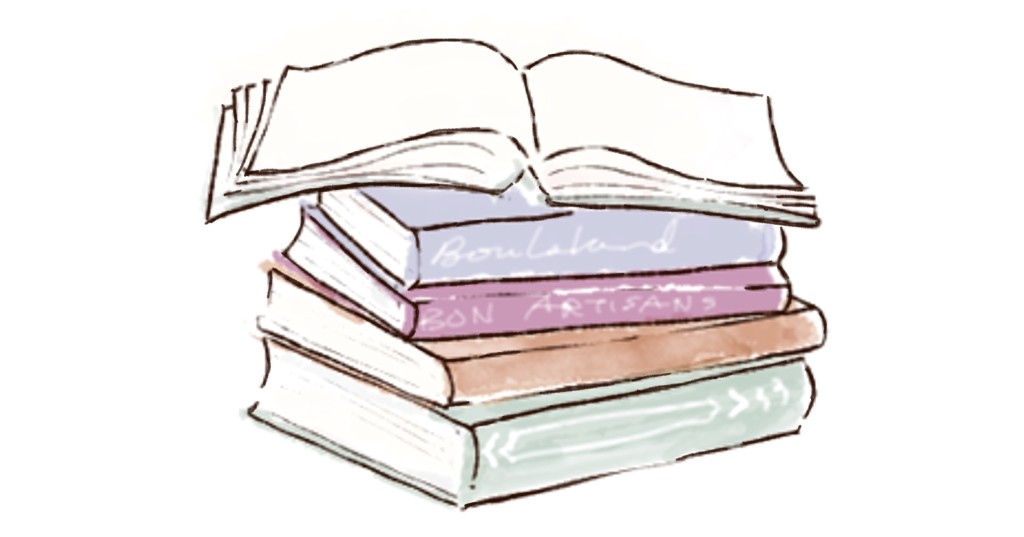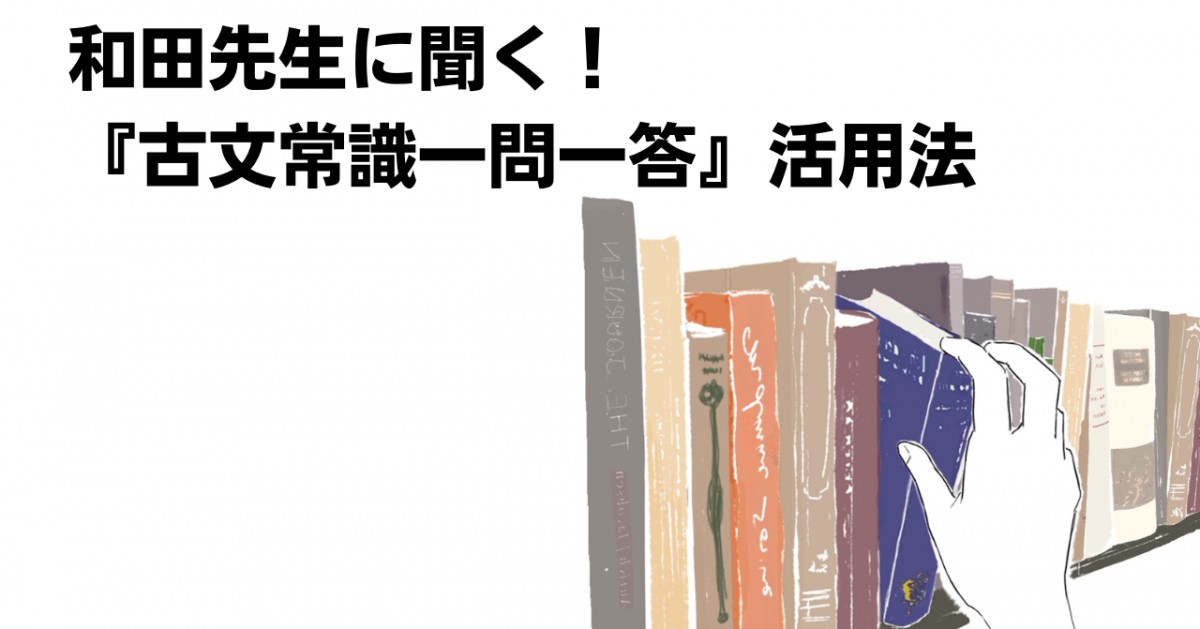#学習方略で生徒の言語化を促す実践①
こんばんは、シン・中の人、一ノ瀬(@mAjorstep_jp)です。
寒くなってきて、コートを着て出かけるのですが、満員電車に乗ると暑くて、でもコートを脱ぐスペースもなく…結局具合が悪くなって目的地に到着…なんてことがあります。電車はもはや冷房をつけて欲しいレベルなのですが、みなさんはいかがでしょうか。最近は自動空調になっている車両も多いようですが、満員電車はとにかく暑いです!!(鉄道会社に届け)
さて、今号はβ版ニュースレターとの連動企画第四弾です。β版でも紹介される#学習方略の原則について、サポメン版では実際に現場でどう使えるのか?を深掘りしていきます。
模試や定期テスト、あるいは年度末の個人成績表などを返却する際に、一人ずつ時間をとって返すという学校も多いはずです。その時に、みなさんはどんな声かけをしていますか?「今回はどこがダメだったと思う?」というようにざっくりした質問をしていませんか?
今回の記事では、仮想の生徒と先生のやり取りを提示しながら、どのような点に気を付けて、どんな話をすればいいのか、お伝えしていきます。その前に、まずは根岸先生からご挨拶です。
メイジャーステップの根岸です。X:@DiceK_Negishi
β版でもお伝えしましたが、来年1月9日に #小論文添削ライブ202601 を開催します。根岸の添削をリアルタイムで配信。添削員根岸が何をどのように見ているのか。その一部始終が「ダダ漏れ」です。
他人が添削している様子をまじまじと見ることってありませんよね。でも、添削のプロセスに先生の学びが隠されていると思うんですよ。きっと根岸が身につけている技術だけでなく、普段意識していないクセレベルまで公開することになります。皆さんの学びのためならさらし者になる覚悟です。ぜひいらしてください。
例年のお正月イベントと同様に、お年玉プレゼントもあります。参加してくださった方から抽選で、ニュースレターで紹介する参考書を差し上げます! 先日のわだじゅんの『古文常識一問一答』はもちろんのこと、12月には小論文・現代文の新刊・名作を紹介します。こちらもお楽しみに。
申込は11/28から。今しばらくお待ちくださいませ。
さて、サポメン版では具体的・実践的な指導例・教材例をお届けしております。今回は生徒とのやりとりです。
-
「余計なことを言ってしまった……」
-
「なぜあれを言わなかったんだろうか……」
-
「生徒との間の壁を取り払えない……」
-
「ずけずけと踏み込みすぎた……」
-
「私が生徒の気持ちを決めつけて戸惑わせてしまったのでは?」
生徒とのコミュニケーションには悩みが尽きないですよね。もちろん根岸もいつも悪戦苦闘しています。民間カウンセラー資格もいちおう取ってますし、個別指導や質問対応は苦手ではないですが、それでもコミュニケーション、特に学習プロセスに関するやりとりは難しいです。
この記事が先生方のコミュニケーションの悩みに対して少しだけですが答えを示していると思います。
タイプ別声かけ実践例
①「原因の具体化」タイプ:上昇傾向を言語化させる声かけ
②「失敗の可視化」タイプ:結果の評価ではなくプロセス分析へ
③「マイルストーンの設定」タイプ:小さな実践目標を言語化
今回は、以上の3タイプ別にそれぞれどのような声かけをすると有効であるかを解説していきます。
そして大前提として、
質問ではできる限り生徒が話すよう聞き役に徹しましょう。話しているうちに自己解決することもあるし、こちらに問題の原因が見えてくることもある。質問は指導ではなくカウンセリング。 #学習方略の原則
という学習方略を念頭において話を進めていきたいと思います。
「原因の具体化」タイプ:上昇傾向を言語化させる声かけ
まず取り上げるのは、成績が伸びている子に対しての声かけ事例です。目的は、「うまくいった要因を明確化し、再現可能な学びに変える」ということです。