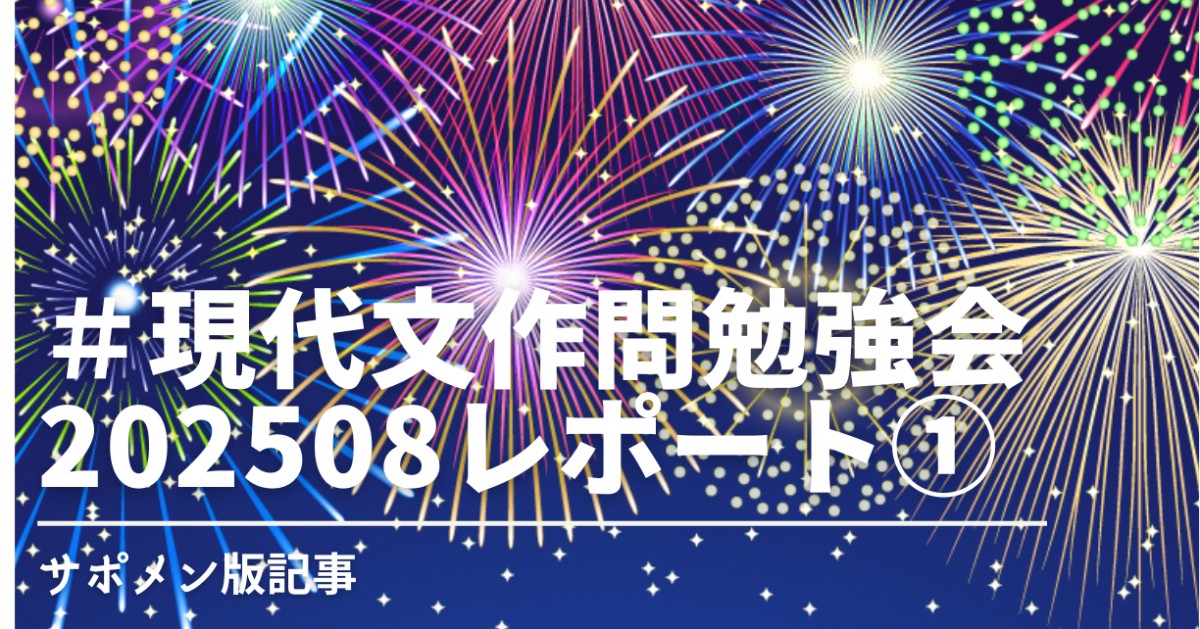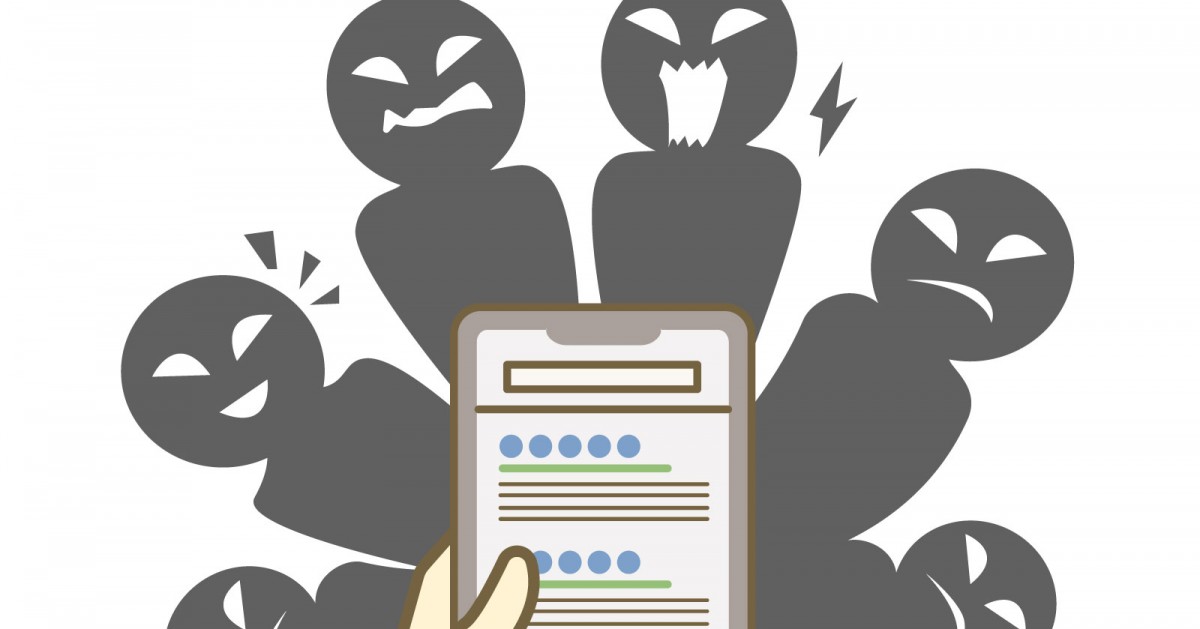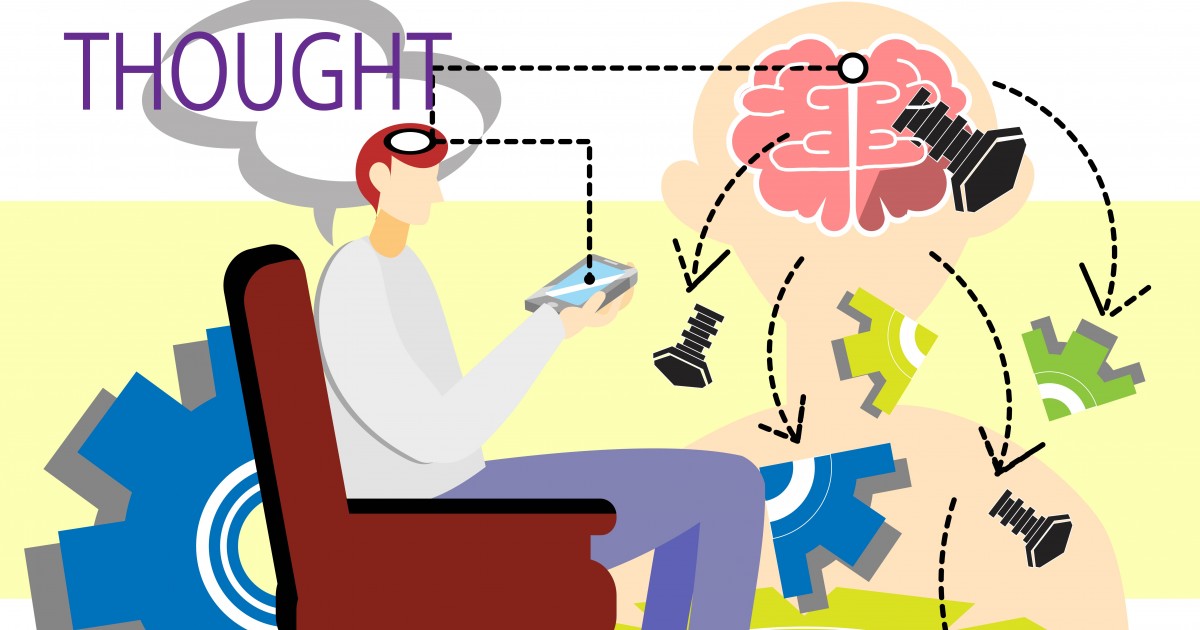問いが先か、答えが先か~作問勉強会に向けて~
こんばんは。シン・中の人(@mAjorstep_jp)一ノ瀬です。
長いようであっという間だったお盆休み、皆さまリフレッシュできましたでしょうか。一ノ瀬は久しぶりに甥っ子姪っ子に会い、圧倒的親戚おばさんムーブをかましてきました。満足です。スムーズな2学期の幕開けを迎えるべく、残りの夏休みも充実したものにしていきましょう。
さて、今週末に迫った#現代文作問勉強会202508に向けて、過去に行われた作問講義の内容を一部抜粋してお届けします。作問勉強会にご参加予定の方も、そうでない方も、作問の基礎を学べる貴重な機会だと思いますので、ぜひご一読ください! お申し込みはこちらからどうぞ。
作問の出発点
問題作成の出発点は「生徒に答えさせたいこと」を明確にすること。
▶読解問題は「答えが先」
まず本文から導きたい答えを定め、そのために適切な問いを作ります。もちろん問いと答えが同時に出てくるのが最も理想的。ただし、先に問いがあって答えを探すのは愚策。作問にかなり苦労するはずです。 .
▶意見論述問題は「問いが先」
開かれた問いを設定し、生徒の思考を広げます。オープンエンド度合いの調整がカギ。ある程度解答の方向性を絞りたいなら、問い方に工夫が必要になります。一方で生徒の発想や着眼を見たいならざっくり問うのがよいです。何を評価したいのかによって問い方が変わってきます。だから問いが先なのです。