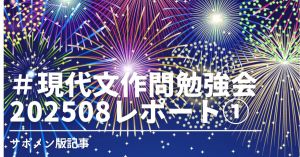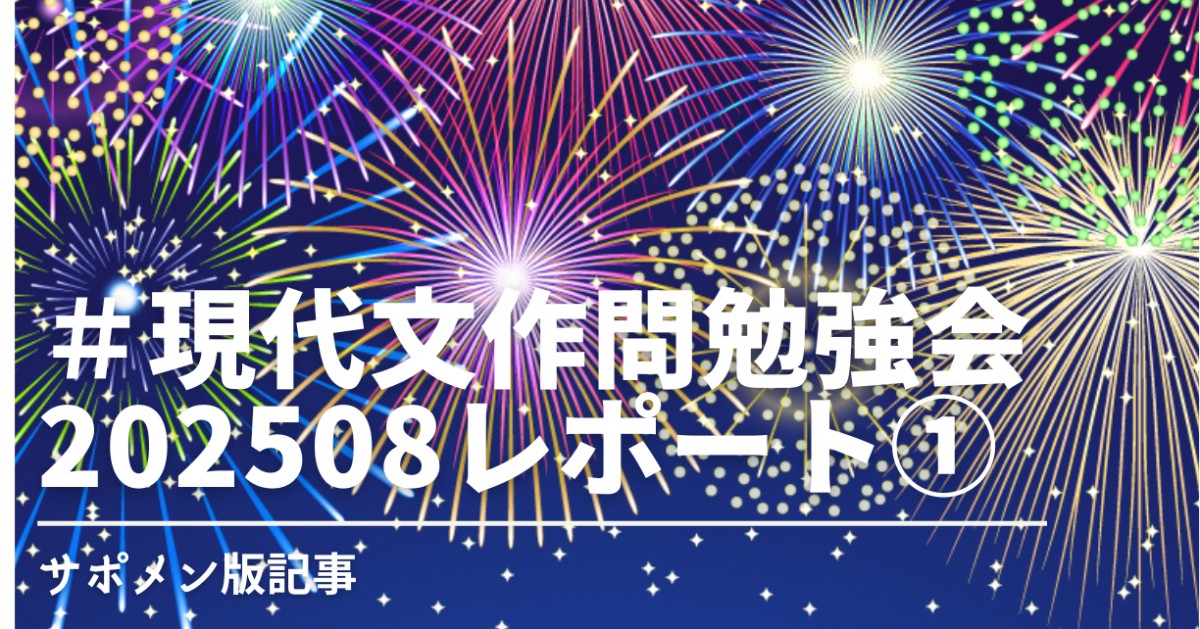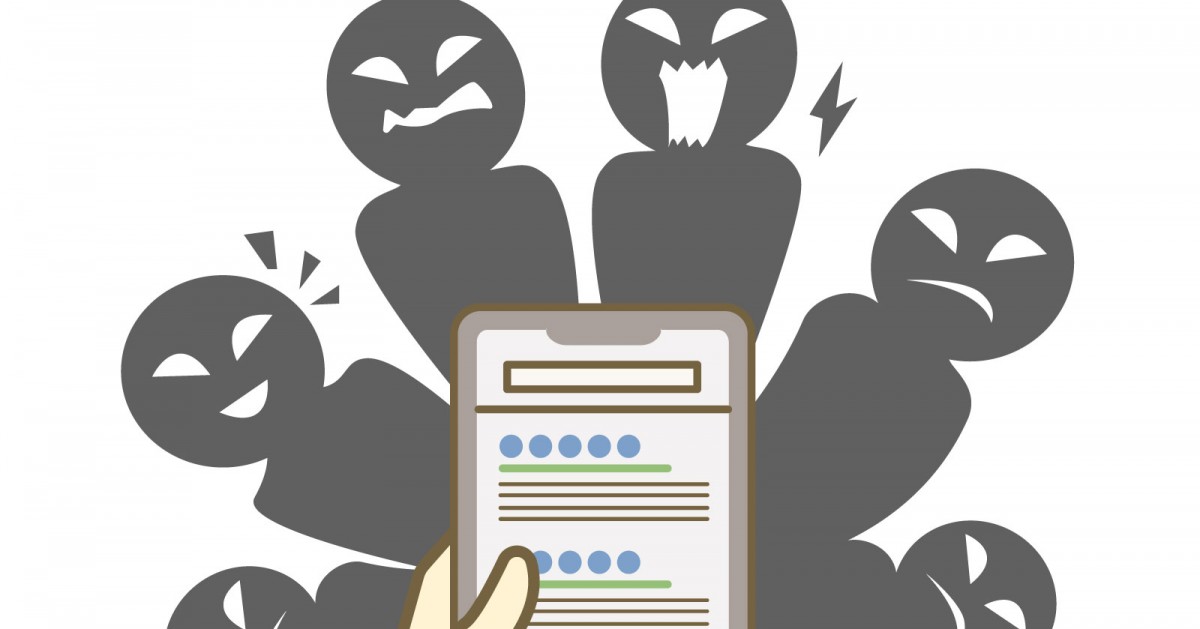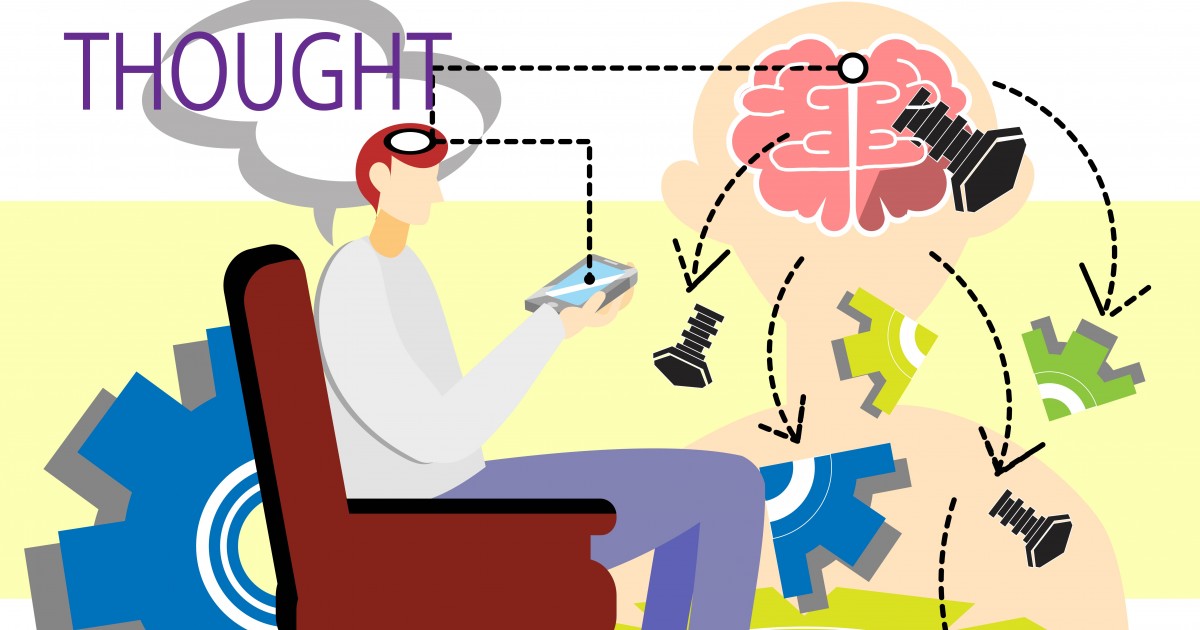誤答づくりのワザ
こんばんは、中の人(@mAjorstep_jp)です。中学校の教員である主人の夏休みが終了したのに、幼稚園児の娘はまだ夏休みで、1週間がとても長く感じました。先生方もまだ暑さが厳しく、お疲れのところだと思います。娘が歯磨きをしても虫歯だらけで甘いものが果物以外消えてしまって、脳みそがエネルギーを欲しています。先ほど、主人が娘を連れ出してくれた隙にコンビニに走ってクーリッシュのベルギーチョコレート味を買って食べました。美味しいのでエナジーチャージにオススメです。
先日#現代文作問勉強会202508 が開催され、無事盛況に終えることができました。討議を重ねるなかで「選択肢を作るのが苦手なので、どのような段階を経てこのようにできたのか知りたい。」と普段の作問で悩んでいることを相談したり、「自分がうまくできなかった部分を上手に説明している作問だな」と他の参加者の作問の仕方を見て感心したりする様子が見られました。
参加者の皆さんは、お互いに自分の意見や疑問を率直に出し合いながら学び合う姿を見て、「このように学び続ける先生に娘を見てもらいたい」と中の人は感じました。
たくさんのトピックが挙がったなかで、興味深いテーマの中からピックアップしてニュースレター会員の皆さんと共有します。
今回の素材文は柳宗悦の「美の国と民藝」から3400字の抜粋です。ぜひご一読してみてください。
サポートメンバーの方は実際に使った抜粋部分と、勉強会で話題に上がったトピックについて根岸先生のお考えをシリーズでまとめています。
サポメンの方は、作問をしてご送付いただくと根岸先生から講評がもらえます。
また、こちらの記事単体でも勉強会の面白さは伝わると思いますが、併せてご覧になるとより理解が深まると思いますので、この機会にサポートメンバーのご登録をよろしくお願いします!
誤答づくりのヒント
選択肢を作る際に正答はすぐに思いつくけど、その後に誤答を作るのが大変でどうしたらいいか、とお悩みの先生がいました。
誤答づくりはたしかに難しいですよね。
何度か勉強会に参加されている先生は、まず記述で正答を作り、本文と照らし合わせながらどのようにずらしていくかを考えるそうです。
①想定する正答を作り、②傍線部を引き、③想定解を別の表現に置き換えていくという流れです。そして、生徒が誤るであろう解答を考えるんだとか。
今回の素材文自体が要領を得ない部分が多い割に、対比構造自体は明確だったので、選択肢がシンプルになりがちだと感じながらも、カチッと字数の揃った選択肢を作り、作問の美学を魅せていました。
誤答づくりの際には以前、勉強会に参加した他の先生の言葉を引用して「愛すべきおバカちゃん」を頭に思い浮かべて作問をしているそうです。