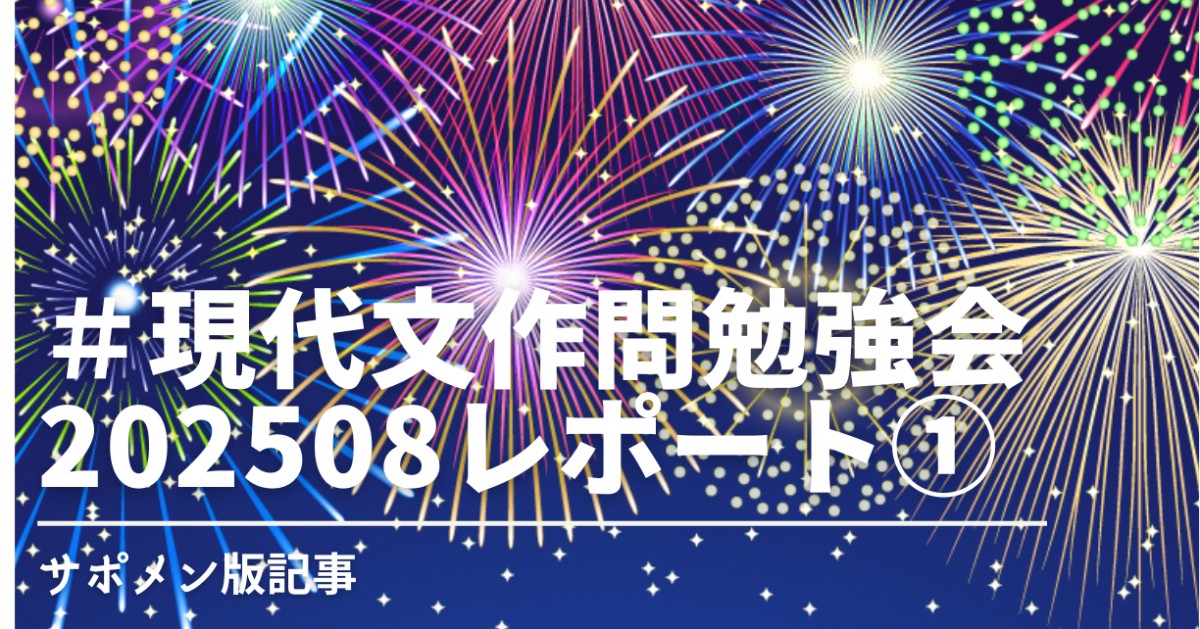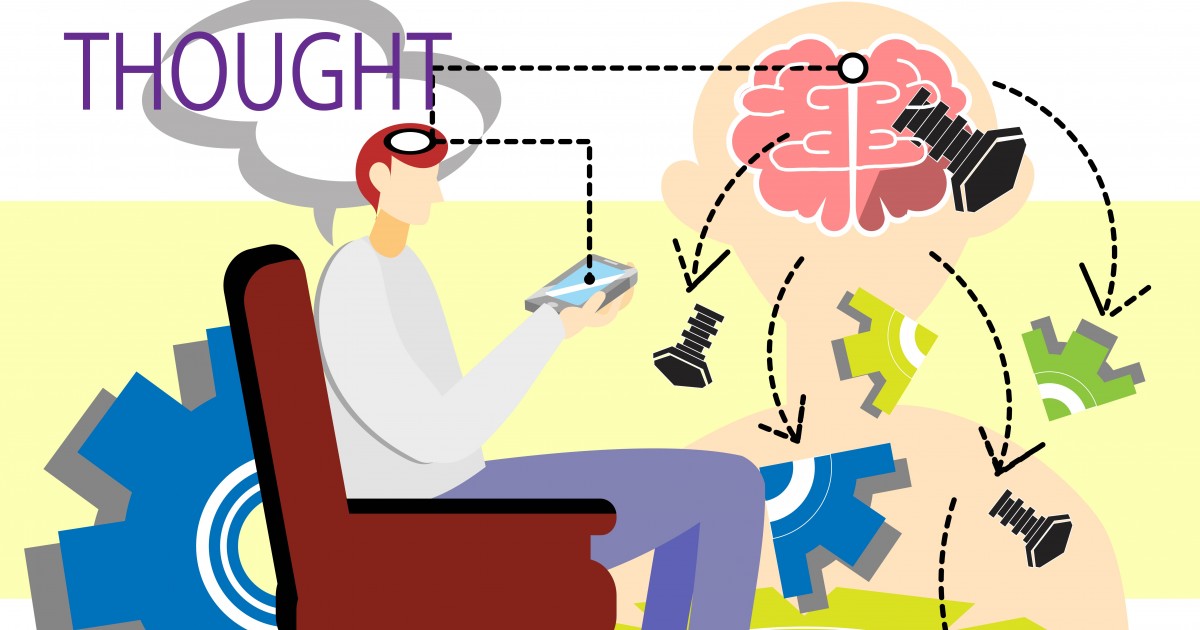他の先生の指導に疑問を抱いたら
こんばんは、中の人(@mAjorstep_jp)です。
お盆休みは実家に帰り、数年ぶりに地域の盆踊り大会&仮装大会に娘を連れて行ってきました。盆踊りに流れている音楽や振り付けは、地域に根ざしていた絹の制作工程が由来です。
娘には河童の仮装をさせました。河童の好物がきゅうりと言われるのは水神へのお供えからくるそうです。祭事にはそのような民俗学的な要素が多分に含まれているので、興味深いですね。
#現代文作問勉強会202508 の参加申込みの締め切りも間近になりました。お盆休みでオフモードになった脳みそを刺激して、新学期からの好スタートのきっかけにしませんか?
詳細はこちらです。
たくさんのご参加をお待ちしております。
今回はこちらの質問への回答です。
いつも記事を興味深く拝見しております。 当方、予備校で小論文の指導をすることが多いのですが、受験生の在籍する高校の先生の指導方針と私の指導方針が異なり、戸惑うことがあります。 私の指導では、次のような形で指導をしております。 ・序論本論結論の三部構成が基本 ・設問で求められない限りは自分の体験は基本的に書かない ・「譲歩逆接(確かに…しかし~)」はむやみに使わない 一方、学校の先生の方では、「起承転結を用いなさい」、「オリジナリティを出すために自分のエピソードを必ず書きなさい」、「譲歩逆接を用いれば論理性が高まる」といった指導がなされることがありました。 学校ではこう、予備校ではこう、と指導されると生徒も混乱してしまいます。 根岸先生はこういうときにどのように対応されますか? また、これは予備校目線ではなく学校目線でも語れることかと思います。その点についてもご意見を伺えればと存じます。
メイジャーステップ根岸です。Twitter:@DiceK_Negishi
ご質問ありがとうございます。予備校の小論文の先生なのですね。
「学校の先生が指導していることがおかしい」というニュアンスを懸命に抑えようとする表現がとてもうれしいです。意識しないといかんところですからね、われわれは。
一方、ここで取り上げられている先生は「塾講師がよけいなことを教えているせいで生徒が混乱して困る」と思っていることでしょう。指導が食い違うときには、どうしても相手の方がおかしいと思ってしまいます。
かなり重たい質問だと思うので、前後編2回に分けてお答えしますね。前編はこうした齟齬の原因は何かというテーマでお送りします。考え方が違うから、と言ってしまえばそれまでなのですが、せっかくなのでもう一段掘り下げます。
私にはこんな経験があります。