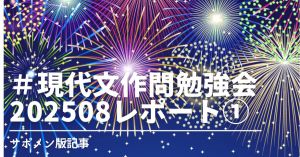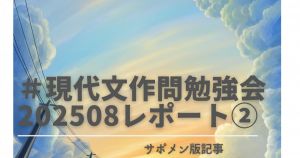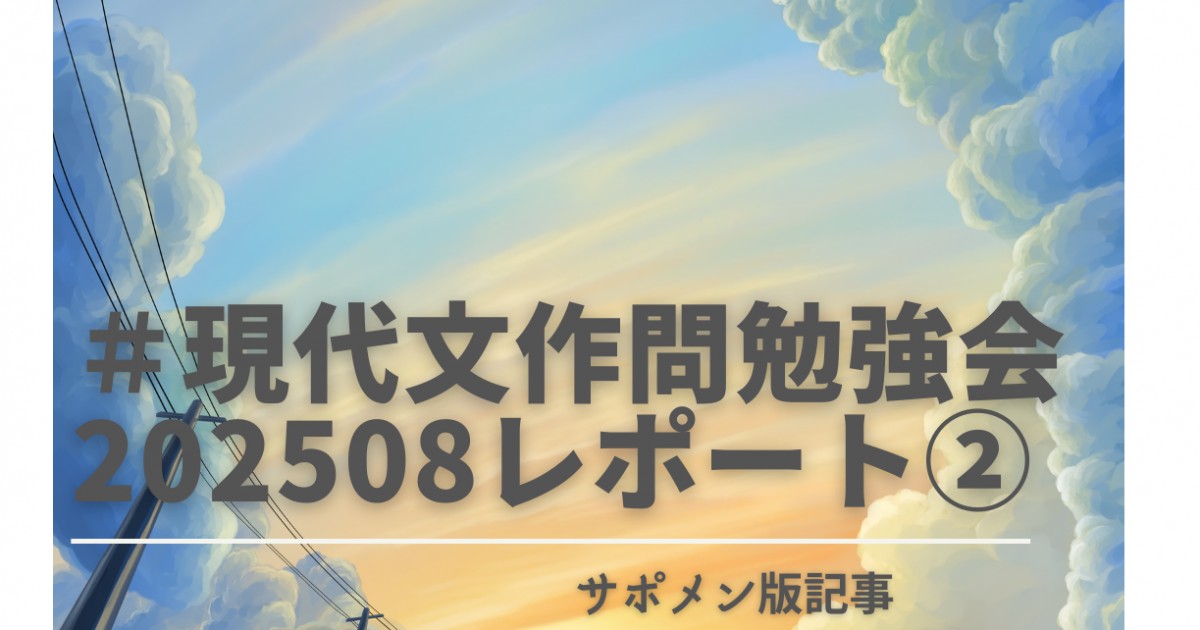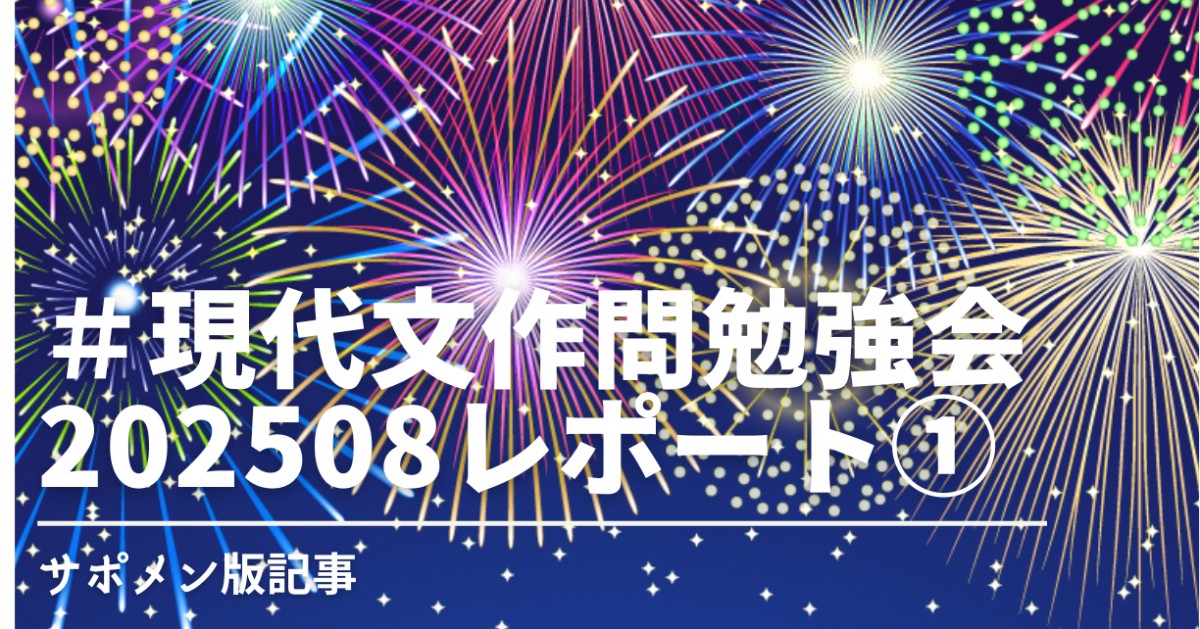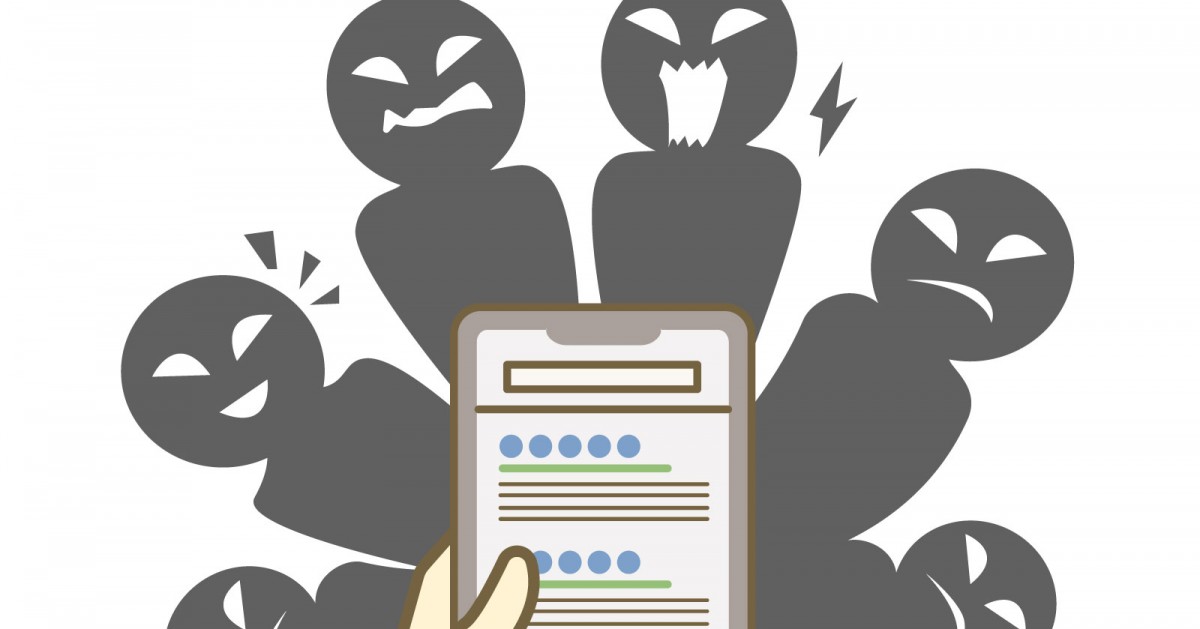採点基準の設定と採点の負担軽減
こんばんは、中の人(@mAjorstep_jp)です。先日、友人の結婚式に招待されて娘と一緒に参列して参りました。中の人は割とリセット症候群気味? で、現状生活に関わりがない場合はエネルギーが足りないので積極的に関わることはしないスタンスです。だからかなり懐かしの人たちと会うことができてとても嬉しかったです。
さて、今回は前回に引き続き先日行われた#現代文作問勉強会202508 の様子をお届けします。
前回の記事はこちら
サポートメンバー向けにさらに濃い解説記事もありますのでぜひ併せてご覧ください。
またサポメンの方は、作問をしてご送付いただくと根岸先生から講評がもらえます。この機会にぜひサポートメンバーに! ご検討のほどどうぞよろしくお願いします。
採点基準を設定し、模範解答をセットで作問をすると思います。作問の内容について深めるともに採点基準について盛り上がりました。その様子をお届けします。
参加者の中に私学で教えている方がいました。私学にお勤めの方や地方の自治体にお勤めの方は分かると思いますが、先生の異動がない・少ないのでベテランと若手との関係が変わりません。都市部の公立学校で中堅にあたる年齢でもずっと「若手」になります。
ベテランの先生がメインで作問をしていて作問の経験が積み重ねられないという悩みが今回の勉強会の参加の動機になったそうです。現状に甘んじず、自分で経験を積み重ねたいと意欲をもっている姿が素敵ですね。
記述問題を担当している先生が想定解答をいくつも作るうえに、「この要素があったら◯点」と採点の基準を示してくださるんだそうです。担当教科を複数人で教えている場合、全ての回答者に対してブレがないように公平な採点をする、ということは「評価」という行為を行ううえで大切な姿勢ですよね。
でも、参加者の先生は、そのベテラン先生のようにできていない、ベテラン先生が引退されたあと誰かが後継するのか、それとも後継をせず別の方法をとるのかと悩んでいました。
そこで根岸先生からズバリ一言