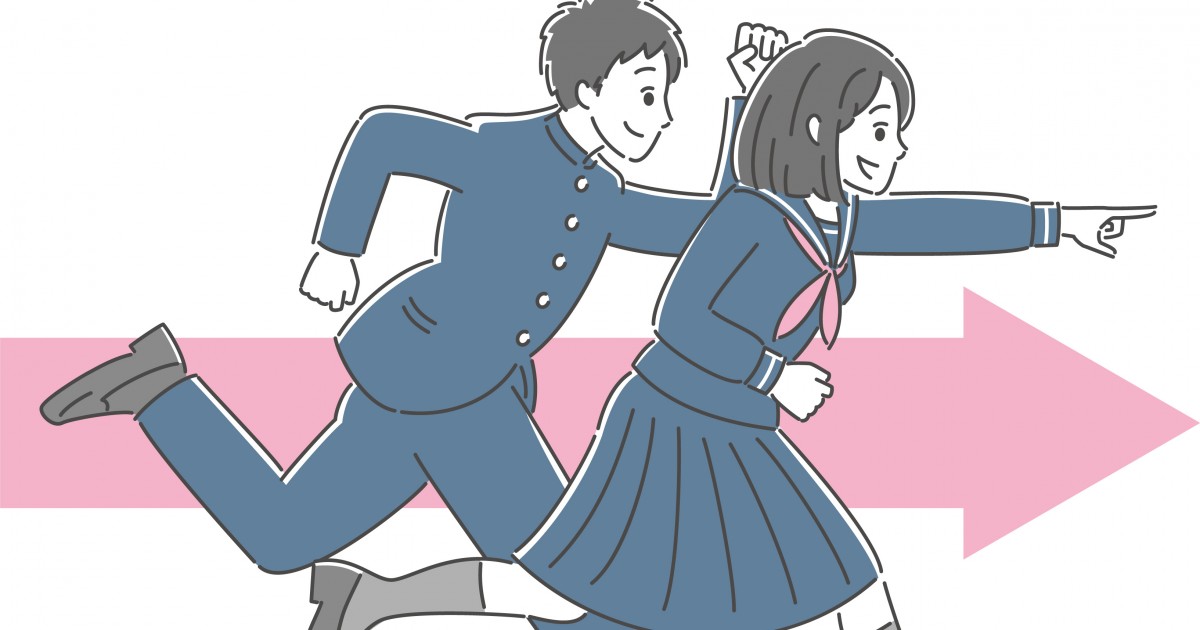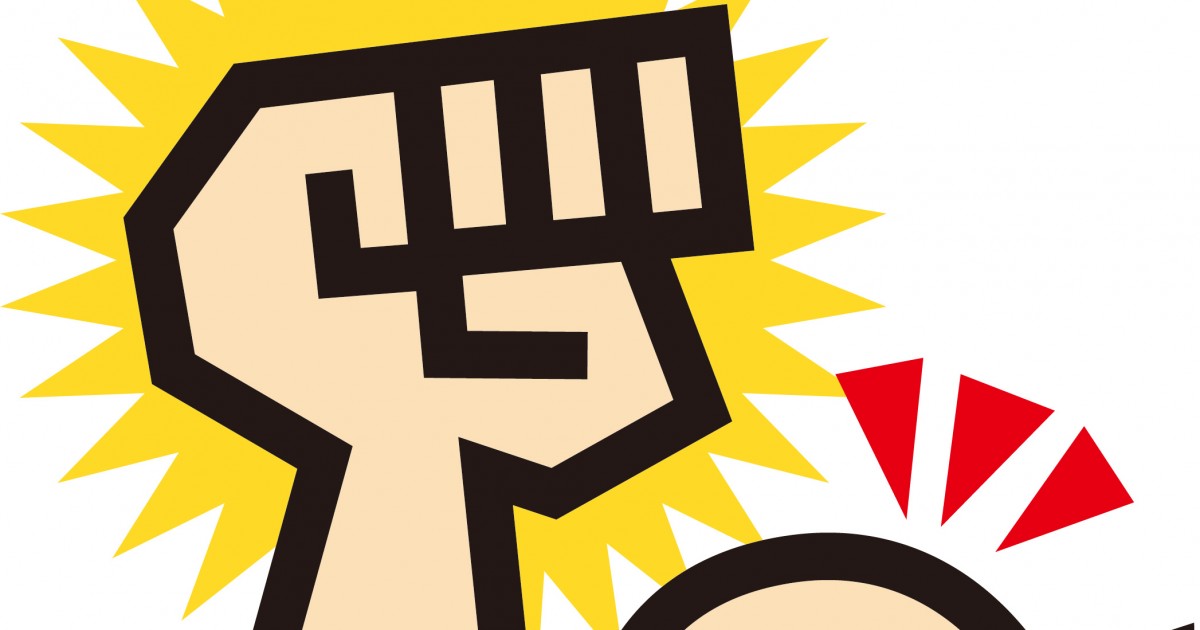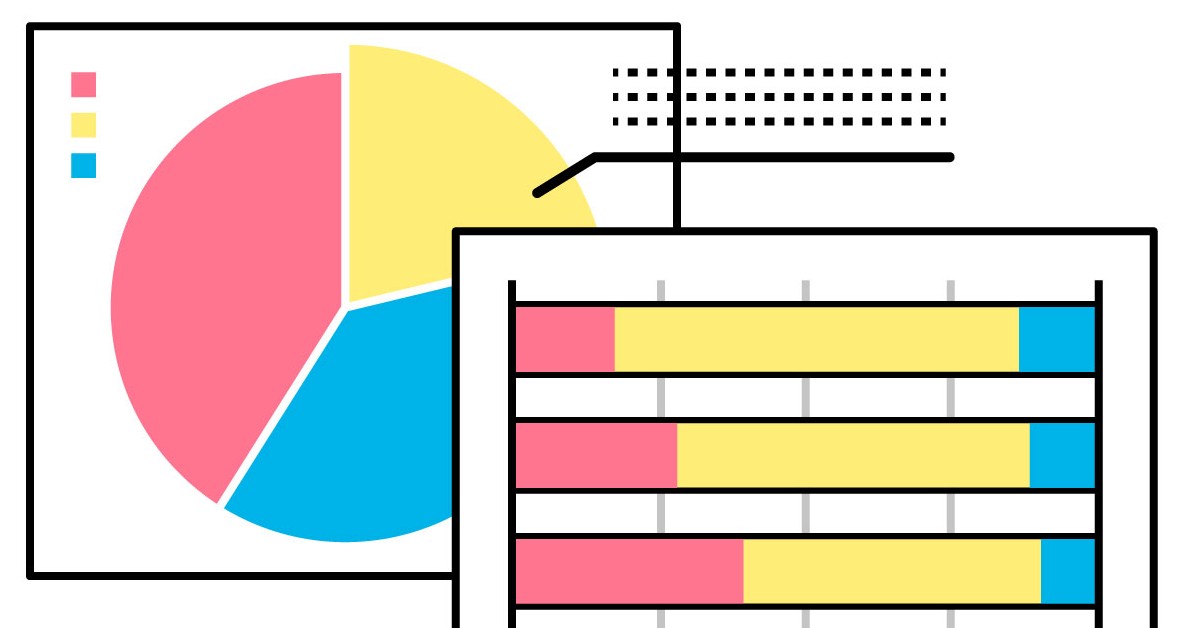#国語作問フェス2025 講師紹介・参加者へのメッセージ
こんばんは、中の人(@mAjorstep_jp)です。
新年度が始まりバタバタしていることもありますが、春の陽気もあり少々気持ちが浮ついています。何より先週お知らせした#国語作問フェス2025 が楽しみでなりません。
ニュースレター会員の方からも、「専門は現代文だけど、古文も漢文もテストは作らないといけないから助かる」「受験対策という観点からも作問者の考えを垣間見るというよい体験ができます」といったお声が寄せられています。
早速サポートメンバーになっていただいた方も。スタッフ一同、さらなる気合が入ります。
#国語作問フェス2025 開催決定のお知らせと、フェス参加にもお得なサポートメンバー登録のご案内はこちら
※申し込みの手順を誤りますと特典が受けられませんので、必ず最後までお読みになってください。
今号では、#国語作問フェス2025 にご登壇される講師の先生方から参加者や参加をご検討されている方にメッセージをいただいていますので、先生方のご経歴と併せてご紹介いたします。
現代文 安達 雄大先生

河合塾・河合塾マナビスの現代文科講師。主に成績上位層対象の講座を担当。模試作成会議への参加、参考書の執筆を通じて、数々の作問現場を体験。著書に『「読める」「解ける」を可視化する 安達の視える現代文』等。
漱石が「夢十夜」で描いた運慶が躊躇なく木から仁王を彫り出したように、あらかじめ文章の方に埋まっている問題を、作る前からそれと見抜いてサクサクと掘り出すことができれば……。これは作問者なら誰しもが抱く夢です。
しかし、我々は運慶ではありません。「問題の出来/不出来は作ってみないと分からない」……これは作問者なら誰でも痛感している真理です。「見抜く」力だけではなく、「掘り出す」技術を磨く必要があります。
ところで、この2つのうち「見抜く」の方は、「本から本へとをさまよいつつ、降りてくる天啓を待つべし」と言うより他ありません。というわけで、本日の講演の主題は、「見抜く」の方ではなく「掘り出す」の方……特にその具体的な手順です。
文章を選び、然るべき字数・範囲で切り取り、線を引き、あるいは穴を空け、設問文(疑問文)の表現を慎重に選びつつ問いを立て、選択肢を作る……。このように、作問は種々様々な作業内容からなります。重要なのは、そうした作業内容の「優先順位」、「順番」です。そこを間違えると、本来ならば受験生たちに現代文についての有意義な知見を与えられたはずの文章が、その真価を損なうおそれさえあります。
せっかくの「仁王」ごと素材を粉砕してしまうことのないよう、本日は皆様に、作問の作業過程を追体験していただきたいと思います。
古文 和田 純一先生

大学在学中から予備校の教壇に上り、河合塾古文科専任講師・代々木ゼミナール講師などを経て、現在はハイスクール@willや学びエイドなどの映像講義、各地の高校などの教壇に立つ。著書は、『ゼロからわかる 古文常識 一問一答』(KADOKAWA)、『まる覚え 古文文法ノート』(KADOKAWA)、『私大マーク対応 古文過去問題集』(桐原書店)、『中堅私大古文演習』(河合出版・共著)など多数。
みなさん、こんにちは。わだじゅんです。予備校で古文を講義し始めて30年以上の月日が流れました。実は根岸先生は優秀な教え子の一人でもあります。そんな彼からこういう機会をいただきまして、感慨ひとしおです。
わたくしは河合塾や代ゼミでは講義の前線に立つとともに、模試作成もしておりました。全国模試作成の現場での出典選び、設問の構成や作問のポイント、文章のどこを切り取り、真の実力を計るため何を問うか・・・・そんな隠された部分をいろいろとお話したいと思います。新課程になってはじめての共通テストの考察も含めて、今後の入試問題の展望も語ります。
今回の講演で微力ながら現場の先生方の手助けになればとも考えております。わずかな時間ですがお付き合いいただけましたら幸いです。
漢文 寺師 貴憲先生

寺師貴憲。漢文講師。東進ハイスクールなどに出講。年間多数の模試に関わる作問のプロフェッショナルでもある。『最短10時間で9割取れる共通テスト漢文のスゴ技』など著書多数。
みなさん、はじめまして。漢文講師歴25年超のベテラン寺師貴憲です。毎年、共通テストや難関国公立・私大の問題を研究して、解答速報を作り、解答解説を書き、模試を作り、講義をしています。
受験漢文の三本柱は、①書き下し問題、②口語訳問題、③説明問題・内容一致問題です。ここに単語の読み・意味、空欄補充、返り点、文学史などが加わります。受験生は「句形」さえ覚えれば十分だと思いがちですが、実際は句形だけで解ける問題はわずかです。それは共通テストを数年分見るだけでも明らかです。
でも受験生は、「『将』は『まさに…んとす』」や「『豈』は『豈に…んや』」といった単純化した知識を好み、しかもうろ覚えなので、やや複雑な問題や記述式になると正答率は大きく下がります。
私は模試作成や答案添削を通じて、受験生が「どこでつまずくか」を把握しています。逆に言えば、受験漢文を攻略するためには「受験生にどのような力をつけさせるべきか」も、ある程度わかっているつもりです。そうした経験を踏まえ、私が普段どのような点を意識して作問しているのかをお話しします。先生方にとっては当然の内容かもしれませんが、そうした中にも、何か今後の漢文作問に役立つヒントが1つでも2つでもあればいいなと考えています。
小論文 根岸 大輔先生

小論文塾メイジャーステップ代表。学びエイド鉄人講師。『身近なテーマで考える力をやしなう 小論文はじめの一歩』著者。小論文・現代文・総合型選抜・学校推薦型選抜の受験指導のかたわら、教材制作、ニュースレター発行、教員向けイベントの企画・制作も行う教育総合プロダクションを運営。
#国語作問フェス2025 開催にあたり、多数のご期待の声をいただき誠にありがとうございます。参加される皆様に資する講演になるようがんばります。
ところで、小論文の作問ってどういうものなのでしょうか。やるべきことは課題文を選んで、問いを立てて、解答例を作り、評価基準を作る。概ねこれくらいです。このうち、最も難しいのはどれだと思います? 多くの方が評価基準の作成だと考えるのではないでしょうか。もちろん難しいのですが、生徒の答案が集まってくればわりとすぐまとまります。
作問者として本当にしんどいのは課題文選択。学校の授業であれば教科書の文章を使うことも多いのではないでしょうか。しかし、複数のテクストを課題文に使用する場合は、どういうテクストを組み合わせるか非常に頭を悩ませます。もちろん教科書をメインテクストにするとして、サブテクストをどうするか。なかなか難しいですね。
そこで、フェス当日はその組み合わせを考える際のヒントをお話しようと思います。キーワードは「タテ」と「ヨコ」。資料を見ていただければ「なるほど!」となっていただけるのではないかと思います。詳細は当日に。お待ちしております。
いかがでしたでしょうか。中の人は学生時代に戻ったようなウキウキを抑えきれません。各分野の講師の先生からノウハウや分野ごとの違いを学びたいな、と感じています。
常にアンテナを張り巡らせて当ニュースレターにたどり着く、学びに前のめりな先生方と一緒に勉強できる日が今から楽しみです。
サポートメンバーについてのご案内
当ニュースレターのサポートメンバー登録のご案内です。サポートメンバーに登録すると、小論文の添削スキルの配信のみならず、勉強会の会費無料でのご案内や先行受付といったお礼もご用意しています。
※宣伝文句を使いすぎると別のフォルダに送信されてケースが多く寄せられています。お手数ですが、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
X(旧Twitter)のDMを公開しています。指導の悩みや素朴な疑問、開催してほしい勉強会(一緒に企画しましょう!)のリクエストも歓迎です。ドシドシ送ってください。会員の皆さんの声が私たちのニュースレター発信の原動力です。
根岸Twitter:@DiceK_Negishi 小論文塾メイジャーステップTwitter:@majorstep_jp
すでに登録済みの方は こちら