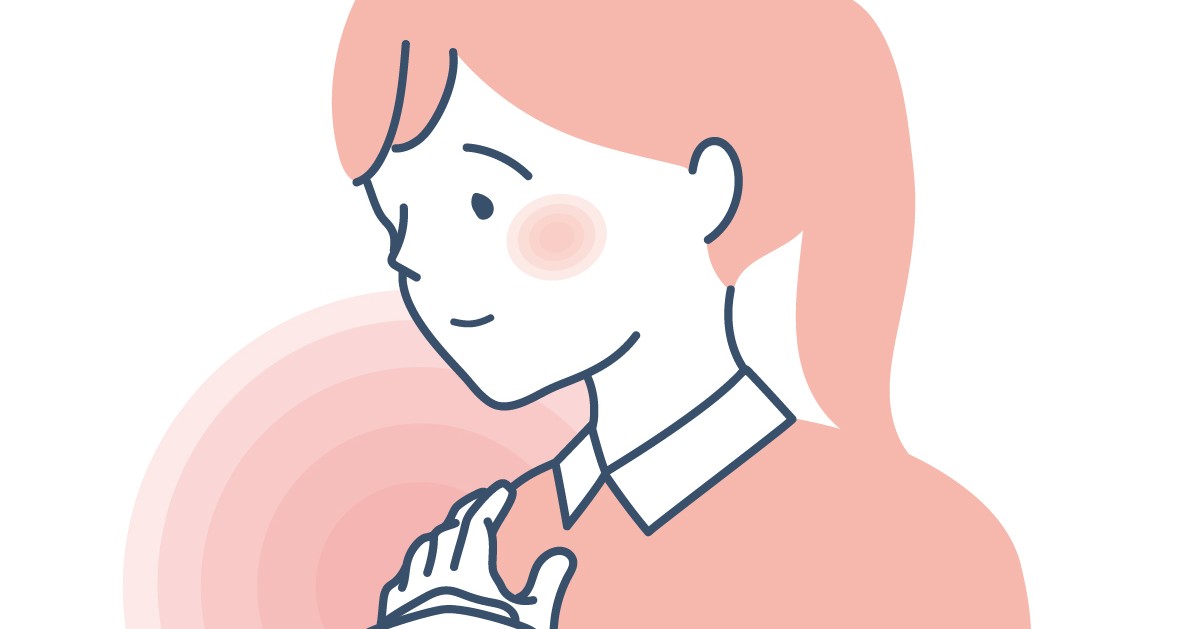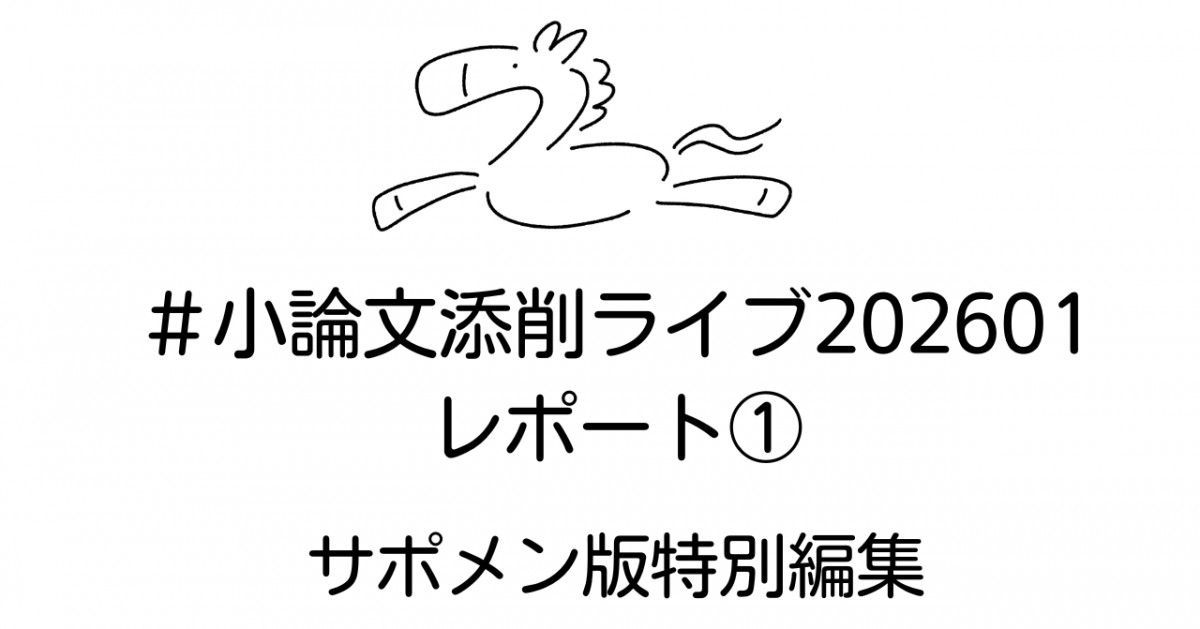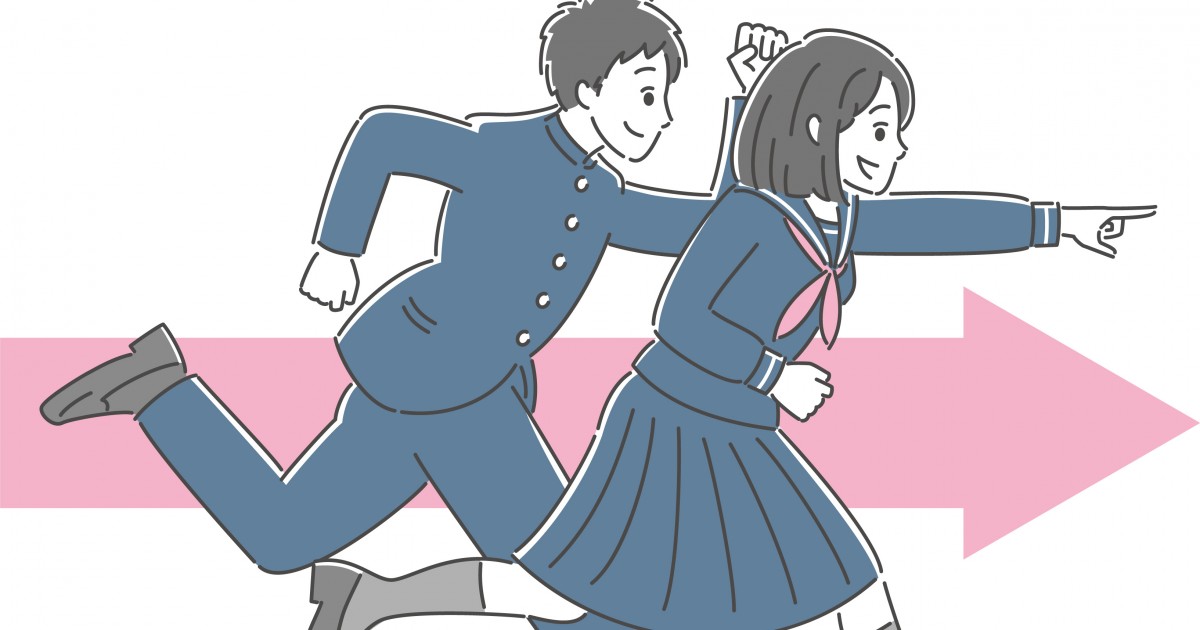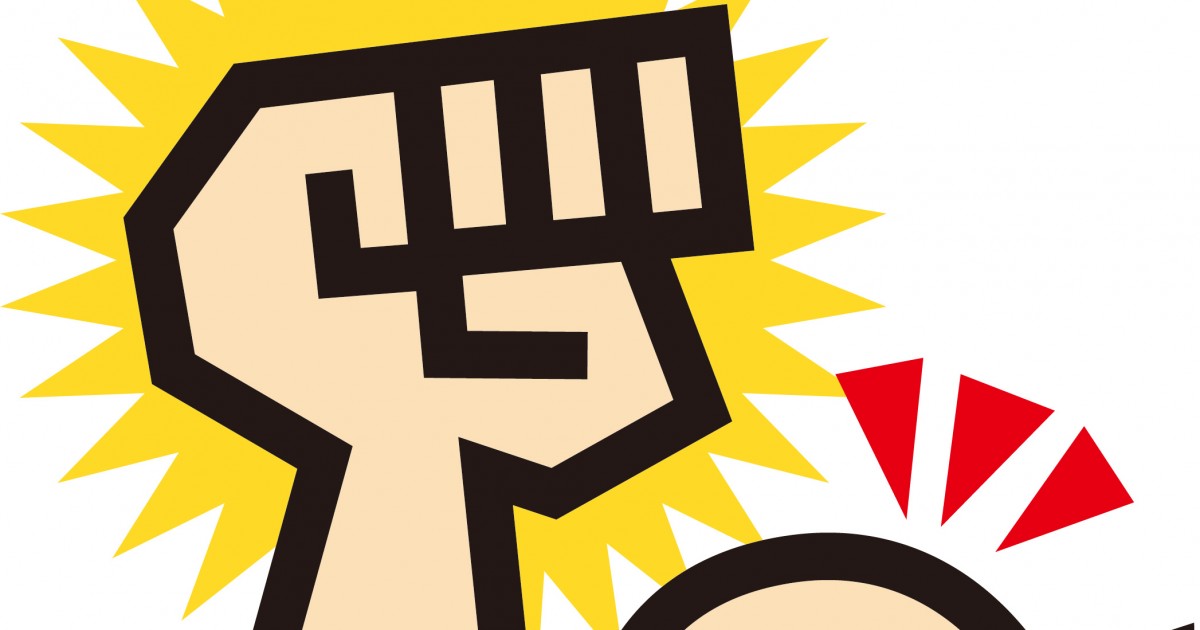議論をすれば、アイデアが湧く
こんばんは、中の人(@mAjorstep_jp)です。
ダイエットを始めて順調に体重が落ち始めました。でも、気が緩むのか出先ですぐに何かを食べてしまいます。
最近は、娘のいない場合のお昼ご飯は、アク抜き不要のしらたきを使って冷麺や坦々麺に変えたり、ソファに座るなら必ず筋トレの類を軽く行ったりするようにしています。
梅雨明けとなり、もう夏休みも目前ですね。先日、根岸先生と打ち合わせを行いました。
もう既にお伝えしている通りですが、8月23日(土)の夜に#現代文作問勉強会202508 を行います。詳細が徐々に決まってきております。7月25日発行のニュースレターにてお申し込み開始を予定しています。まずはスケジュールをあけておいてくださいね。
さて、最近会員になった方は当ニュースレター、小論文・現代文の指導スキルを学ぶ会(β版)主催の勉強会ではどのようなことを行っているか知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
作問勉強会はキャッキャウフフの会です
校内や自治体で行われる授業研究会で行われる授業では、なかなか真似ができない授業が展開されていませんか? 練りに練った授業が繰り広げられ、派手さが際立っていて取り入れることが難しいこともしばしばありますよね。作問も同じように悩みが尽きない、とのお話をよく伺います。ベテランの先生のテストや模試を見れば勉強になるけれど、本当に欲しい、次の定期考査にすぐ活かせるものとなると……と若手もベテランも悩んでいる声が届いています。
そこでできたのが当ニュースレター主催の作問勉強会です。
チャリタブルな(charitable:慈善の・寛大な)心で、ベテランも若手も全員が顔を突き合わせて、お互いの作問を楽しみながらブラッシュアップします。
作問勉強会では人数が多かった場合は、討議ルームを作り、それぞれが持ち寄った作問の検討会が行われます。
今回は、作問に欠かせない選択肢問題と記述式問題についてどんな討議になったのかお伝えします!
そもそも誤答ってどうやって編み出すの?
想像してください。あなたは定期考査、あるいは模擬試験の作問をすることになりました。素材文から問題にしたい部分を洗い出し、どこに傍線を引くか決めました。
「傍線部Aはどういうことか。説明として最も適当なものを次のア~オのうちから一つ選び、記号で答えよ。」 設問文もできました。
では、あなたはどのように選択肢を作りますか?

画像の通り、頭の上に???が浮かんでしまう方もいるのではないでしょうか。
討議の中ではいくつかの方法が議題になりました。